面接の場にふさわしい「最近読んだ本」って何? 質問意図を知って回答しよう
頻出質問ではないものの、面接で「最近読んだ本はありますか?」と聞かれることがあります。そんなときに、どんな本を挙げれば良いか迷うかもしれません。現役就活生たちも、どんな種類の本を紹介すれば、面接官の好印象につながるか悩んだようです。
この記事では、「最近読んだ本」の回答の仕方と例文、就活生におすすめの本15選、「最近読んだ本」の質問で面接官が見ているポイントまで一気に解説します。質問の意図がわかれば、面接官に自分の魅力をアピールすることができるでしょう。
| 就活生の5大不安を解決!
オススメのツール5選 |
|
|---|---|
| ツール名 | 特徴 |
| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |
| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |
| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |
| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |
| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |
就活生に質問! 面接で「最近読んだ本は何ですか?」と聞かれたことはある?
早速、就活生たちがどんな業界や企業で、「最近読んだ本はありますか?」と聞かれたのか確認しましょう。どんな本を読んだと答えたのかも答えてくれました。
また、どんな本を挙げるのが面接に相応しいのか迷うという人は、参考にしてみてくださいね。

面接で最近読んだ本は何ですかと聞かれたことはありますか。

出版業界とIT業界で聞かれた覚えがあります。そのときは「運動脳」という本や「USJのジェットコースターは何故後ろ向きに走ったのか?」という本を紹介していました。
面接官の意図を知ろう! 面接で「最近読んだ本は何ですか」と聞く3つの意図

就活生の回答から、定番質問ではないものの、さまざまな業界・企業で「最近読んだ本」の質問がされるとわかりましたね。では、なぜ面接官は「最近読んだ本」の質問をするのでしょうか。ここからは、「最近読んだ本」の質問をする意図を紹介していきます。
面接官の意図に沿った回答ができれば、面接を通過できる可能性が上がるかもしれませんよ。
①読書習慣の有無を知るため
多くの知識を習得できること、多様な価値観を知れることが読書のメリットです。面接官は「最近読んだ本」の質問で学生に日頃から読書習慣があるかを確認して、学生の学習意欲や知的好奇心の有無を知ろうとしています。
読書をして知識がつくと、周りの社員や取引先と円滑なコミュニケーションを取れるようになることも多いため、社会人になってからも読書をする習慣があると良いですね。
②学生の人となりを知るため
読書の嗜好性から、どんなものに興味がある学生なのかを知ろうとする意図もあります。たとえば、スポーツを題材にした本を読んだ学生であれば、「スポーツに興味がある学生なのかな?」「この学生は、困難を乗り越えるストーリーが好きなのかな?」と想像することができるでしょう。
学生と既存社員の嗜好性が近ければ、根底にある価値観や物事への感じ方が似ている可能性もあります。学生と企業のマッチ度合いも垣間見える質問だと覚えておきましょう。
学生の人となりを知る質問として、特技を教えてくださいという質問もあります。この質問も、どんな特技を伝えれば良いのかと迷いますよね。以下の記事を参考に事前に対策をして、面接に臨みましょう。
面白い特技の探し方・伝え方
おもしろい特技28選|ネタに走ると危険? 特技の探し方や伝え方
面接の特技の回答例
回答例70選|面接での「特技」の答え方! 就活生の実回答付き
③プレゼンテーション能力を図るため
「最近読んだ本」の質問では、どれだけその本を魅力的に伝えられるかも見られています。仕事では、自社の製品や自分の提案を相手にアピールして、選んでもらうことが必要な場面もあるため、その素質を見ようとする意図もあると言えますね。
皆さんの人柄や発信力を活かして、面接官に「面白そうだな」と思ってもらえるような回答を作ることを意識しましょう。
「自分を一言で表すと何ですか」という質問においても、学生のプレゼンテーション力の高さが見られています。その一言で、どれだけ自分自身を魅力的に見せられる学生なのかを、面接官は図ろうとしています。事前に対策をして記憶に残る一言を伝えましょう。
「最近読んだ本」は合否に直接関係しない! 面接準備の一つとして対策はしておこう
前提として、就活では本人のスキルや適性でのみ合否を判断するべきであると、厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では唱えられています。その観点で、「最近読んだ本」に関する質問は本人のスキルとは関係ない質問であると捉えられるため、合否に直結する可能性は低いです。
そのため、志望動機などの頻出質問と比べても聞かれる頻度は少ないでしょう。ただし、用意していない質問をされて、頭が真っ白にならないためにも準備しておくことがおすすめです。「学生の人柄を知りたい」と面接官が感じている場合、アイスブレイクとして聞かれる可能性もあるので、面接準備の一つとして対策していきましょう。
「最近読んだ本」の質問と同様に、「大切にしている価値観」や「座右の銘」の質問も面接の合否とは直結しない質問です。しかし、想定外の質問をされて必要以上に焦ってしまうという事態を避けるためにも、予習をしておきましょう。
本質を理解できていない? 「最近読んだ本は何ですか」に回答するときの勘違い

「最近読んだ本」の質問では、学生の嗜好性や価値観を知りたいという意図がありました。そのため、もしその回答に嘘があると、入社後に企業とのミスマッチが起こる可能性もあるのです。
ここから紹介する3つの誤解に当てはまらないよう、この質問の本質を理解した回答を作りましょう。
①読んだ本の内容で評価される
「志望企業や業界に通ずる内容の本が良いのではないか」「小説よりも、ビジネス書や専門書が良いだろう」など、選んだ本で評価が変わるのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、どんな本を選んだのかよりも、「なぜその本を選んだのか」「その本から何を感じたのか」の方が見られています。
この記事でも、「最近読んだ本」の回答では、学生の人柄や嗜好性、発信力などが見られていると解説しましたね。つまり、学生自身のことを知りたいという考えの方が強いと覚えておきましょう。
②実際に読んでいなくても問題ない
「面接官に評価されそうな本を読んだことにしておけば良い」と考えている人もいるでしょう。しかし、面接官はこの質問から学生の価値観を知ろうとしているため、嘘の情報を伝えてしまうと、学生の考えを正確に捉えることができません。
さらに、その本についての深掘り質問をされたときに答えられないと、実際に読んでいないことがばれてしまうケースもあります。答えがわからない質問をされて困らないように、面接では実際に読んだ本を挙げるようにしましょう。
③ただ自分の好きな本を伝えれば良い
面接では、「この本が好きです」とだけ伝えたり、本の紹介だけ伝えたりするのは避けましょう。この質問で面接官が知りたいのは、「なぜこの本が好きなのか」「その本から何を学んだのか」ということです。そのため、これまでの回答と一貫性のある本を選んで、アピールポイントの後押しをしましょう。
たとえば、努力ができる性格をアピールしていたのにもかかわらず、「努力をしなくても成果を上げられる方法」などといった本を紹介してしまうと、一貫性が保てなくなりますよね。これまでに伝えた内容と、紹介する本の印象にズレがないかを確認するようにしてくださいね。
実際に読んで面接に臨もう! 就活生におすすめの本15選
「最近読んだ本」の回答で重要なのは、「どんな考えで、その本を選んだのか」ということだとわかりましたね。だからこそ、皆さんがアピールしたい像にあわせて、最近読んだ本を選ぶことが大切です。
ここからは、どんな本を選ぼうか迷っている人向けに、「就活生におすすめの本15選」を紹介します。本から感じられるイメージと、面接官に伝えたい像が一致しているかどうかを考えて選んでみてくださいね。
なお、本記事で紹介している本に関しては、話題性や知名度などを加味して、HR team PLUS編集部で厳選しています。あくまで一例として参考にしてみてくださいね。
①ビジネス
社会人になる準備の一環として、ビジネススキルや知識を身に付けられる本を読んで、学習意欲をアピールするのも良いでしょう。下記の5つの本から、志望企業や業界、職種で求められるスキルが学べる本を選んで、企業での再現性の高さをアピールしてみてくださいね。
おすすめのビジネス書①
①世界の一流は「雑談」で何を話しているのか
著者:ピョートル・フェリクス・グジバチ
発行年:2023年
取引先との商談や、日常の会議における雑談力を高めるための一冊です。社内外における円滑な人間関係の構築、プロジェクトの推進など、雑談にはビジネスを効率的に進めるヒントが隠れています。この本を読めば、雑談を駆使して、仕事で効率的に成果を出す方法が学べますよ。
おすすめのビジネス書②
②苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」
著者:森岡毅
発行年:2019年
経営危機にあったUSJを再起させた、森岡毅がマーケティングのノウハウから社会人としての生き方までを語る、ビジネス書です。自分が納得するキャリアを形成するうえで、たとえ辛くとも、自分の信念を持つことがいかに大事かがわかるでしょう。自己理解の一環としておすすめしたい一冊です。
おすすめのビジネス書③
③入社1年目の教科書
著者:岩瀬大輔
発行年:2011年
新入社員から転職者まで、入社1年目に求められるビジネスマナーやスキルを一挙に紹介してくれる一冊です。1年目からスタートダッシュを切って、社会人として成功を収めたいという人はこの本を読んで、意欲の高さをアピールすることができるでしょう。
おすすめのビジネス書④
④パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法
著者:安藤広大
発行年:2024年
この本では、すべての社会人に必要な「決断を先延ばしにしないためのマインドの持ち方」を学ぶことができます。社会人になると決断の一つひとつに責任がともなうため、消極的になる人も多いですが、この本を読めば、決断をすることが苦手な人も、勇気ある決断を下せるようになるでしょう。
おすすめのビジネス書⑤
⑤1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術
著者:伊藤 羊一
発行年:2018年
著者の伊藤洋一の体験談をもとに、1分で伝えたいことが伝わるプレゼンテーション力を身に付けられる一冊です。誰かに物事を伝えるときは、「協力してほしいこと」や「教えてほしいこと」があることが大半でしょう。この本を読めば、自分が望む行動を返してもらうためには、大事なことをシンプルに伝える力が必要だとわかるはずですよ。
②小説
小説からは、皆さんの性格そのものをアピールすることができます。「努力をすることの大切さを知っているからこそ、逆転劇を描いた小説が好き」と伝えられれば、皆さんの人となりと回答に一貫性が生まれますよね。下記の5つの作品から、自分の性格や価値観に通ずるものを選んでみてくださいね。
おすすめの小説①
①成瀬は天下を取りにいく
著者:宮島未奈
発行年:2024年
主人公である成瀬あかりの天真爛漫さから繰り広げられる、青春奮闘劇を描いた一冊です。200歳まで生きるという大きすぎる目標を掲げながらも、持ち前の行動力で前人未踏の結果を出していく成瀬に勇気をもらう人も多いでしょう。行動力をアピールしたい人にはおすすめの一冊だといえますよ。
おすすめの小説②
②武道館
著者:朝井リョウ
発行年:2015年
武道館を目指すアイドルグループの葛藤を描いた一冊です。小説に登場するアイドルグループのように、何かを成し遂げたければ、ときに大きな挑戦が必要になる場面もあります。しかし、その挑戦に対して肯定的な意見だけがもらえるわけではなく、否定的な言葉をかけてくる人もいるでしょう。周りに振り回されてしまうことが多いという人は、この小説を読んで自分を信じることの大切さを感じてみてください。
おすすめの小説③
③コーヒーが冷めないうちに
著者:川口俊和
発行年:2015年
喫茶店を舞台に、時空を行き来しながら過去の後悔や過ちと向き合っていくストーリーです。小説のなかでは「過去にああしておけば良かった」という後悔から過去に戻り、相手とのわだかまりを解消していくシーンがあります。実際には、過去に戻ることは難しいからこそ、この小説を読むと今行動することの重要性を感じられるかもしれません。
おすすめの小説④
④人魚の眠る家
著者:東野圭吾
発行年:2015年
小学生の娘が水泳の授業中に溺れ、植物状態になってしまうという衝撃の展開から始まる一冊です。植物状態になる娘をどう生かすべきなのかという夫婦の葛藤から、「人として生きるということ」「親として子を育てること」「法整備について」を考えさせられるでしょう。社会に対する責任を負う社会人になる準備として、社会問題に向き合ってみることがおすすめです。
おすすめの小説⑤
⑤イニシエーションラブ
著者:乾くるみ
発行年:2007年
登場人物のマユが「たっくん」と交際をする様子を描いた小説。しかし、この小説は単なる恋愛小説ではなく、「たっくん」を介しておこなわれる恋愛ミステリー小説なのです。自分が手掛けた仕事で、周りの人をあっと驚かせたいと思っている人は、ぜひこの小説からヒントを得てくださいね。
③自己啓発
企業で活躍する人材になるには、自分に自信を持つことも大切です。その観点から、自分に足りない部分を自己啓発本で鍛えて、社会人として成功をしたいという意思を伝えるのも良いですね。どんな社会人でありたいかを考えながら、下記の5つから読むべき本を選んでみてくださいね。
おすすめの自己啓発①
①嫌われる勇気
著者:岸見 一郎/古賀 史健
発行年:2013年
アルフレッド・アドラー心理学について学べる一冊です。「嫌われるのが怖くて、人間関係の悩みが尽きない」という人はぜひ読んでみてください。周りにいる人が敵か味方なのかを決めるのも、どうありたいかを決めるのもすべて自分です。嫌われる勇気を持てば、自分を幸せにできるかもしれませんよ。
おすすめの自己啓発②
②なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学
著者:和田秀樹
発行年:2022年
この本では、人生がうまくいく人が意識している考え方のコツを学ぶことができます。どんなときでも笑顔で明るく過ごすことが、社会人になってからの皆さんを救うかもしれません。ネガティブ思考な人こそこの本を読んで、企業で活躍できる社会人になれるように準備を進めましょう。
おすすめの自己啓発③
③喜ばれる人になりなさい 母が残してくれた、たった1つの大切なこと
著者:永松茂久
発行年:2021年
著者と母の生きた歴史を綴った一冊です。著者の母は、自分が「応援される人」になれば周りも幸せであるから、喜ばれる人になりなさいと語っています。自分がやることに自信が持てないという人は、誰を喜ばせる人になりたいという軸で生きると生きやすいかもしれませんね。
おすすめの自己啓発④
④朝イチの「ひとり時間」が人生を変える
著者:キム・ユジン
発行年:2023年
結果を出してきたビジネスパーソンたちがおこなってきた、朝の時間を活用して人生を充実させる方法を学べます。大学生になると、生活の時間が不規則になる人も多いでしょう。誰かが休んでいる時間に行動することが、社会人として成功するうえでの秘訣かもしれませんよ。
おすすめの自己啓発⑤
⑤わたしが「わたし」を助けに行こう 自分を救う心理学
著書:橋本翔太
発行年:2024年
皆さんが「できない」と思い込んでいることを「できる」に変える一冊です。今持っている悩みは、「できない」という理由を作るためだけに存在している悩みかもしれません。やりたいことがあるのに挑戦できないという人は、ぜひ読んでみてくださいね。
面接で実践しよう! 最近読んだ本の回答手順

どんな本を選ぶか迷ったときは、自分が伝えたい像から逆算して、紹介する本を選ぶことがおすすめです。紹介する本が決まったら、面接の回答を組み立てていきましょう。この記事で紹介する4ステップに倣うと、面接官が聞きたい内容を網羅できる回答になりますよ。
ステップ①どんな本を読んだのか要約をする
まずは、その本がどんな本であるのか簡単に説明することが必要です。説明をする際は、いつ・どこで・誰が・何をしてどうなるストーリーなのかを説明すると良いでしょう。ただし、本の要約は回答のメインではないため、一文で収められる内容に抑えるのが適切だといえます。
どのように要約するのかは、「仕上げに確認しよう! 面接で最近読んだ本の回答例文15選」で確認してみてくださいね。
ステップ②なぜその本を読んだのかを伝える
「〇〇をテーマにした、〇〇(作品名)という本を読みました」と伝えられたら、アピールしたい像から逸れないように、その本を読んだ理由を伝えましょう。たとえば、「私は人の温かさに触れることが好きなので、この本を読みました」など、伝えたい人柄が感じられる内容だと良いですね。
その本を選んだ理由を伝えるときは、自己分析の内容をもとに伝えることがポイントです。そのため、自己分析の内容を一度振り返ってから、伝えたいイメージに合っている本を選ぶことができているかも確認しましょう。
ステップ③読後に何を感じたのかを話す
次に、「その本を読んでどんな感情になったか」「何を学んだのか」を伝え、皆さんの考え方や価値観を伝えましょう。ステップ②と同様に、伝えたいイメージから逸れない内容を伝えることがポイントです。
「私も誰かの心を動かせる人になりたいと思った」「何かを成し遂げるには周りの人の協力が必要だと感じた」など、仕事を連想させる感想であれば、なお良いでしょう。皆さんの持っている価値観が、志望企業でも活かせそうだと感じてもらえれば採用に近づきますよ。
ステップ④本で得た知識を入社後どう活かすかをアピールする
最後に、ステップ③で感じたことを入社後どう活かすかを伝えて、皆さんが企業で活躍できる存在だとアピールしましょう。企業の求める人物像に沿って伝えると、面接官が入社後のイメージを描きやすいです。
たとえば、「この主人公のように、入社をしてからも日々努力をし続ける人材でありたいと感じました」のように、入社への意欲を感じられる内容を加えるようにしましょう。
面接の場面では、結論ファーストを意識しようといわれますよね。実は、結論ファーストと同様に回答の締め方も重要なポイントです。良い締め方ができないと、「結局何を伝えたかったのだろう」と思われてしまうこともあるため、下記の記事から回答を上手に締める方法を学びましょう。
就活生直伝! 最近読んだ本の回答を魅力的にする方法

なぜその本を読んだのかという点にフォーカスを置いて話すと、ただその本の要約を伝えることにならず、良い回答が作れると思います。
最近読んだ本を答えるときに、まず「その本に〇〇のヒントが書いてあると思ったから読んだ」と伝えましょう。その後に、「実際にはどうだったのか」「その本を読んで何を学んだのか」「考えが変わったのか」などを話します。そのように話すことで、自分の目的意識の高さや知的好奇心をアピールすることができました。
面接官の方も「何が好きなのか」を知りたいわけではないと思うので、「何を感じ取ったのか」を伝えることに重点を置いて話すと良い回答を作成できると思います。
最近読んだ本の面接での回答は発信力×吸収力をアピールすることを意識しよう!
「最近読んだ本」回答では、本の内容を活用して、皆さんの魅力をアピールしましょう。「この本から〇〇という学びを得ているのは、〇〇さんらしいな」と思ってもらえるような回答が理想です。
本の内容を説明するのが目的ではなく、本から得た内容を自分なりに吸収して、皆さん自身の魅力を発信するのが回答のゴールだと覚えておきましょう。
仕上げに確認しよう! 面接で最近読んだ本の回答例文15選
最後に「最近読んだ本」の例文を確認して、自分の作った回答が読みやすい順序になっているか見比べてみましょう。おすすめの本15選で紹介した内容をもとに例文を解説していくので、気になった本があるという人は参考にしてくださいね。
就活生が実際に話した! 「最近読んだ本」の回答例文

最近読んだ本として、灰谷健次郎の「天の瞳」を選びました。破天荒で自由奔放ながらも優しい、倫太郎という少年の成長を見守るシリーズ作品となっています。以下、実際の回答です。
「私が最近読んだ本は灰谷健次郎作、天の瞳です。倫太郎という少年がさまざまな人に出会い、経験を重ねていくことで成長する様子が描かれています。倫太郎は一見粗暴で破天荒ですが、その一方で感受性が強く、幼いながらにも思考が深いため、筋の通った行動をとるところに自分にはない魅力を感じています。若さ故の未熟さや歯痒さ、一方でこれから何にでもなれるという可能性や自由であることの素晴らしさなど、今の自分が忘れていたことを思い出させてくれるよう作品です。自分よりも年下の子供が主人公の作品ですが、その生き様に学べる部分が多く、ときには勇気づけられることもありました。私の生き方を変えてくれるような一冊だと言えます」
ビジネス書の回答例文①
例文
私が最近読んだ本は、『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』です。仕事における雑談の重要性を綴っている本で、私自身も雑談に苦手意識があったため、この本を読むことにしました。
読後には、「職場の人間関係を構築できる」「新たなアイデアを得られる」「仕事を効率化できる」などといった、雑談が持つ効果を感じ取ることができました。自分や周りにもメリットがあるとわかったため、入社後も自分から積極的にコミュニケーションを取り、仕事を円滑に進められるようにしたいです。
自分の苦手を克服しようとする姿勢が見える前向きな例文ですね。なぜこの本を選んだのかという理由も明確で、再現性の高さが見て取れます。
ビジネス書の回答例文②
例文
私は、『苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』という本を読みました。この本は、USJを再建させたことで有名な著者が、娘に対してキャリアを形成するうえでのアドバイスをする本です。
私自身、自分が歩みたいキャリアが本当に自分に合っているのかが不安だったため、この本を読むことにしました。本では、「いかなるときも自分を信じることが大事」と書かれていて、今の自分に足りないものは「プライド」だと感じました。
入社後は、営業職として自社の製品と自分自身のトークに自信を持ち、果敢に挑戦していこうと考えています。
読後の感想から、本で学んだことを自分のキャリアに活かそうとする姿勢が見えますね。本のなかで、自分の弱点を見つけ、それを克服しようとする姿勢にも学生のタフさが現れ、人柄がわかりやすい例文です。
ビジネス書の回答例文③
例文
私が最近読んだのは「入社1年目の教科書」です。この本では、新入社員が身に付けたいビジネスマナーやスキルが網羅されていて、社会人になる準備としてうってつけの一冊だと感じました。
私はアルバイトでミスをしてしまったときに慌てて何もできず、不甲斐ない思いをしたことがあります。それを経て社会人としてどう対応するべきだったのかを学びたく、この本を読みました。
入社後も、「1年目だから」といって甘んじず、社会人として責任のある行動を取っていきたいです。
過去の経験から、明確な意思を持って本を読んでいて、とても説得力があります。失敗をそのままにしない姿勢が、社会人になってからのさまざまな場面でも活きそうですね。
ビジネス書の回答例文④
例文
私は、『パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法』という本を読みました。この本では、仕事においてYESとNOをはっきり伝えるためのマインドセットを学ぶことができました。
私は失敗をすることが怖く、大きな決断から逃げることも多かったです。しかし、この本では「失敗をするのが当たり前」と書かれていて、決断に対して前向きなイメージを持てるようになりました。
入社してからも、自分から手を挙げ、たとえ失敗してもそれを学びとして活かして邁進していきたいです。
自分の今の弱点が、社会人になってからの成長を止めるかもしれないと危惧して、本を手に取ったということがわかりやすいですね。これまでの経験を赤裸々に語ってくれていることからも、素直さがうかがえます。
ビジネス書の回答例文⑤
例文
私が最近読んだのは、「1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術」という本です。この本では、相手に伝えたいことをわかりやすく伝えるための方法を解説しています。
私は、相手にお願いをするということが苦手で、その結果伝わりづらい会話をしてしまうことが多いです。しかし、この本で「相手に提案をすることの本質は、相手を動かすことだ」と書かれていて、つまり相手が何をしたら良いかがわかりやすいように話すことが必要なんだと感じました。
入社してからも、相手の立場に立ったコミュニケーションをすることで、お互いに仕事がしやすい空間を作り上げたいです。
「伝える」ということの本質的な意味を理解できており、入社後も円滑なコミュニケーションをが取れそうな学生に見えます。気遣いができる学生だからこそ、わかりやすく伝えるという力が加われば、活躍の可能性も高そうですね。
小説の回答例文①
例文
私は、「成瀬は天下を取りにいく」という本を読みました。主人公の成瀬が、周りから無謀だといわれた挑戦であっても果敢に食らいつき、結果を残していく姿に心を奪われました。
私は小心者で、大きな挑戦ができない性格でした。一方、主人公の成瀬は、やりたいことをやりたいと宣言して、周りの人の評価を気にせず行動する性格です。私は、そんな成瀬を見て「やらない理由を見つけるのではなく、やる理由を宣言して行動しよう」と思うようになりました。
入社後も、自分の意思や考えを積極的に発信し、理想のキャリアを築くために努力していきます。
挑戦に苦手意識があるからこそ、この本を読んだというのが興味深いですね。本から学び取った内容も、本人の性格に通ずる内容であるため自己分析力の高さが伺えます。
小説の回答例文②
例文
「武道館」という本を読みました。この本は、武道館を目指すアイドルグループの苦悩を描いた作品です。武道館に立つために、良かれと思っておこなったプロモーションで批判を受けたり、人気が出たことで良くない噂が立ったりと、一筋縄ではいかない主人公たちに共感をしました。
私自身も、自分の弱点を克服しようとリーダーに挑戦しようと試みたものの「らしくない」などといって嘲笑されたことがあります。しかし、この小説を読んで自分で選んだ道を正解にしていくことが大切ということを学び、他人よりも自分を信じなくてはいけないんだなと思いました。
入社後も、周りの意見に流されすぎず、自分の意思を持った社会人でありたいなと思います。
この本を読んで、自分のなかに変化があったということがわかりやすい例文ですね。弱点と自覚しているものと、印象的だと感じた一文にも納得感があり、一貫した人柄が伝わってきます。
小説の回答例文③
例文
私が最近読んだのは、「コーヒーが冷めないうちに」という小説です。この小説はタイムトラベルを描いた作品で、登場人物たちが過去の後悔と向き合う様子が印象的でした。
私は、この小説を読んで「過去は変えられないけれど、未来は変えられる」と強く感じました。過去から帰ってきた登場人物が現代を生きる恋人と、自分たちの未来について話し合うシーンから、未来の可能性を開花させられるのは自分しかいないんだと感じたのです。
私は、過去の失敗をひきずってしまう性格なのですが、過去をどれだけ後悔しても、その事実は変わりません。だからこそ、これまでの失敗も学びに変えて、御社においては自分の長所を活かして、新たな価値を生み出せる人材になりたいと思っています。
過去の失敗をポジティブに捉えようとする姿勢が伝わりますね。仕事でも失敗は付き物なので、それを上手く乗り越え安心して仕事を任せられそうという印象が持てるでしょう。
小説の回答例文④
例文
私は「人魚の眠る家」という本を読みました。プールでの水難事故が原因で植物状態になってしまった愛娘と生きる家族を描いた作品です。
知名度があったためこの本を読んだのですが、それ以上に「自分らしく生きられていること」のありがたみを知る機会になりました。植物状態になって親の意思で生かされている瑞穂と自分を対比して、脳や体が生きているうちに主体的に行動をしなくてはならないと強く感じました。
この本を読んで、流されるままに生きてきた自分に対しての後悔が生まれています。だからこそ、入社してからは自分の意思に従って、YES/NOをしっかりと告げられる人になりたいです。
知名度の高さから読んだ本を、自分の学びに変えているところに、学習意欲の高さが見て取れます。入社してからも、周りの社員の働き方を上手に吸収しながら、成長してくれそうですね。
小説の回答例文⑤
例文
私が最近読んだのは、「イニシエーションラブ」という本です。この本は恋愛ミステリー小説で、異なる時期に同姓同名の彼氏と交際していたと思われていたマユが、小説の最後に「実は同時期に二股をしていた」と明らかになる本でした。
私は、エンターテインメント性の高いものが好きなので、話題作ということもありこの本を手に取りました。前評判通り、最後の仕掛けに心を奪われて、小説というものの概念がひっくり返りました。
私も、入社後は既存のものに捉われない広告を作れるように、日ごろから情報収集などをおこない、柔軟性の高い業務ができるようにしたいです。
学生がどんな物に興味を持っているのかがわかりやすい例文ですね。クリエイティブ色の強い業界に行きたい学生であれば、エンターテインメントへの感度の高さが評価されるでしょう。
自己啓発の回答例文①
例文
私は、「嫌われる勇気」という本を読みました。私は心理学を専攻しているため、アドラーの心理学についての見解が語られている本ということもあり、手に取ることにしました。
本のなかでは、「他者から見られている自分を勝手に決めつけているのも、問題を自分事として捉えるのも自分だ」と書かれていました。私は、誰かの評価を気にして、自分にとって意味のない行動をしてしまう傾向にあります。
しかしこの本を読んで、「自分を幸せにするための行動を、自分のためにやろう」と考えるようになりました。社会人になると自分の意見を持つことがより大事になってくると思うので、入社後も自分の軸を持つことの大切さを忘れないようにしたいです。
「自分の軸を持つために、この本を読んだのだろう」と学生の考えが伝わりやすいですね。社会人になってから苦労するであろうことも予測できていて、キャリアを真剣に考えていることが伝わります。
自己啓発の回答例文②
例文
私が読んだのは、『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』という本です。この本では、成功をしている人たちが意識している生き方のコツを学ぶことができました。
なかでも、「明るい人は支持されやすい」という言葉が印象的でした。私は、物事をネガティブに考えてしまう傾向にあったのですが、そのたびに「この人に付いていくのは不安」と思わせてしまっていたのかもしれない感じました。
入社後は、困難なことに対しても可能性を見つけて前向きに取り組める人材でありたいと思っています。
この本を読んで、自分に足りない箇所がわかったと述べていて、自分と向き合う事に対する意欲を感じますね。自分の弱点を改善しようという前向きな姿勢が大変印象的です。
自己啓発の回答例文③
例文
「喜ばれる人になりなさい 母が残してくれた、たった1つの大切なこと」という本を読みました。この本では、「周りが応援したくなるような人になりなさい」と書かれていて、その言葉がとても印象的でした。
私は、「これをやりたい」という意思が強くない性格で、自分の生き方に自信を持てないことが多かったです。しかし、誰かが喜んでくれたら良いなという思いがずっとありました。この本を読んで、「それならとことんまで、誰かを喜ばせられる人間になろう」と思えました。
入社後も、顧客の課題解決にとことんまで奔走し、社内外から応援される人材になりたいと思います。
キャリア形成に対して、自分なりの考えを持てていることがわかります。他者貢献の意欲が強い学生だからこそ、入社後もチームのために活躍してくれるのではないかと期待の高まる例文になっていますね。
自己啓発の回答例文④
例文
私が読んだのは『朝イチの「ひとり時間」が人生を変える』という本です。この本では、偉業を残してきたビジネスパーソンたちは、朝の時間を有効活用して大きな挑戦を成し遂げてきたと書かれていました。
なかでも、「誰かが寝ているときに、誰かは動き出している」という一節が印象的でした。成功する人というのは、「誰かが休んでいるときに、自分の意思で動ける人だ」と強く感じました。
入社してからも、始業前の時間を有効に使って、一日の生産性を上げられる人材になり、御社の成長に貢献していきたいです。
時間の使い方の大切さをわかっている学生で、入社後も効率化して成果を上げられそうという印象になります。ただし、無理をしすぎることは厳禁だとも覚えておいてほしいですね。
自己啓発の回答例文⑤
例文
私が読んだのは、『わたしが「わたし」を助けに行こう 自分を救う心理学』という本です。この本で印象的だったのは、「何かをできないといっているのは、できる可能性を見つけてしまうことを避けるため」という内容でした。
つまり、「できない」は自分が自分を不必要に守っているだけなのだなと感じました。私自身も、海外に留学に行きたいという考えがありながらも、「お金がない」「語学力が低い」などの理由から挑戦から遠ざかるための理由を探していたような気がします。
やらない後悔をしないように、入社後は自分の可能性を信じて挑戦し続けられる人材でありたいなと考えています。
過去の後悔を未来の可能性に変えようとしている例文ですね。この本を読んで、自分の過去の選択を見直すことができていて、振り返り力の高さも感じます。
最近読んだ本の回答で面接官が見るのは発信力と吸収力! 一貫性のある回答で選考通過
ここまで、「最近読んだ本」の質問で面接官が評価している点、回答手順と例文、回答のコツまでを解説してきました。面接官が見ているのは本の内容ではなく、「本から感じ取ったことを話す学生自身の姿」だとわかれば、面接官の意図に沿った回答ができるでしょう。
つまり、ほかの質問回答と同様に「最近読んだ本」の回答でも、伝えたいイメージに合わせて回答を作成しておくべきなのです。一貫性のある回答を作ると、これまでの回答の説得力を上げることができます。面接官の記憶に残る回答で、面接を突破しましょう。

公正な採用選考という観点から、愛読書について聞かれることは近年なくなってきていますが、それでもいざ聞かれた際、どうコミュニケーションするかについて想定・準備しておくことは大事です。
ほかの質問においても同じことが言えますが、面接官が知りたいのは応募者の人柄です。「どのような価値観を持っているのか」「何が強みで何を弱みとしているのか」「どのような思いから経験を積んだのか」などの質問を通して人柄を理解したいと思っています。そのため、この文脈のなかで「最近読んだ本は何か」という質問がなされ得ると考えられます。
何の本をチョイスして、どのように伝えたら良いか迷うときは、「自分のどのような側面を伝えたいか」を出発点に考えてみてください。「なぜその本を手に取ったのか」「読んだ後の感想や行動の変化はあったか」など、自分が企業に伝えたい要素から、読んできた本の種類を選び、回答するのはどうでしょうか。
自分を良く見せようとするのではなく、自分の人柄をもっとよく伝えるための機会として、この質問への回答を考えてみると良いと思います。自己分析も深まるというメリットもありますよ。
就活力診断テストはもう使いましたか?
「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。
面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。
\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/
診断スタート(無料)













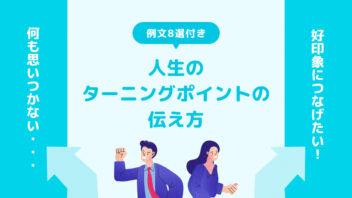
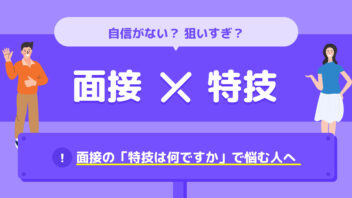


コンサル企業で「最近読んだ本は何ですか?」聞かれました。その際に伝えた本は、「仮設思考」という本です。