自分の将来像を描くには? 入念な準備をして現実的なキャリアプランを設計しよう
「面接で将来像を聞かれたら、何を答えたらいいの?」
「そもそも将来像ってどういうもの……?」
将来像に関する質問は、面接の頻出質問です。しかし、実際にその業界で働いたことのない学生にとって、これはかなりの難問であると言えるでしょう。
しかし、定番の質問である以上、対策する方法もきちんと存在します。この記事では、将来像とは何かという説明から、具体的な業界・職種別の回答例、答えてはいけないNG回答の例まで、幅広く紹介します。
実際に就活を経験した先輩たちのリアルな体験談も紹介しているので、ぜひしっかりチェックしてみてくださいね。
似たようなテーマとして「キャリアプラン」や「キャリアパス」に関する質問が挙げられます。以下の記事でさまざまな回答例を紹介しているので、併せてチェックしてみてください。
| 就活生の5大不安を解決!
オススメのツール5選 |
|
|---|---|
| ツール名 | 特徴 |
| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |
| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |
| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |
| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |
| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |
「将来像」と「将来の目標」の違い|目標に向けて先輩たちが頑張っていることは?
「将来像」と「将来の目標」は、一見似たような言葉ではありますが、その間には微妙なニュアンスの差があります。日常生活であればそこまで厳密に区別する必要はありませんが、就活の面接においては、この2つのどちらを聞かれたかによって答える内容が変わるため、注意が必要です。
将来像
自分が目指す理想の姿。「お客様と深い信頼関係を築ける営業のプロ」のような、自分のキャリアにおける大まかな方向性
将来の目標
将来像を実現させるために設定する具体的な指標。「3年以内に主力商品の専門資格を取得する」のように、具体的な期限とセットで考えるのが一般的
この2つを適切に使い分け、それぞれ設定することによって、理想の将来に向けて着実にステップアップしていけるようになります。面接で将来像について質問された際には「まずは将来像を答え、その後に具体的な目標を述べる」という形で答えると良いでしょう。

あなたの現在の職種とその先に考えられるキャリアの選択について教えてください!

あなたが描いている将来像を教えてください!

私は幅広い国の人々が平等にITの恩恵を受けられる社会を作りたいと考えています。その目標に貢献できる人材になるために、現在はITの基礎知識を深める資格取得に励んでいます。

私には「世界で活躍できる人になりたい」という大まかな目標があります。基礎固めをし、自分のスキルを高めるために、今は資格の取得を目指しています。

情報技術を駆使して社会に価値を創造できる人材になるために、プログラミングやSQLといったデータベース技術について学んでいます。
理想の将来像が定まった時期を聞いてみた!
就職活動において「将来像はいつごろ決めるべきか」という質問をよく耳にします。その時期は人それぞれですが、一般的な就活スケジュールでは、大学3年生の夏から秋にかけて業界研究や企業研究を始め、その過程で自分の将来像を具体化していくケースが多いようです。
しかし、最初から完璧な将来像を描いておく必要はありません。あらかじめ細かく設定していても、インターンシップや会社説明会、面談など、企業との接点を持つうちに、理想の姿が更新されていくことも決して珍しくはないからです。
それでは実際にかつて就活を経験した先輩が「将来像」を定め始めた具体的な時期をチェックしてみましょう。

私の将来像が形になり始めたのは1月ごろでした。それまでは希望する業界の仕事について大まかな内容しかわかっておらず、具体的な部署や仕事内容についてはあまり理解できていませんでした。
きっかけは、OB・OG訪問を繰り返しおこなったことです。さまざまな部署で活躍する先輩社員から、具体的な仕事内容やキャリアについて話を聞くうちに「こんな仕事をする部署があるのか」という新しい発見が増えていき、自分の将来像が少しずつ明確になっていきました。

私は、夏インターンを終えた頃、自分の将来像が形になりました。さまざまな業界や企業のインターンに参加したことで、それぞれの業界や企業の理解が深まり、自然と自分の将来の解像度も上がっていったことがきっかけです。
また、夏のインターン選考に向けておこなっていた自己分析の影響も大きかったです。選考準備や実際の選考経験を通じて、「将来、自分は何がしたいのか」という優先順位が明確になり、結果的に将来に取るべき選択肢が絞られてきました。
幅広い角度から検討しよう! 納得の将来像を描くための4つのアプローチ法
- 自己分析で将来どうしたいか掘り下げる
- 業界研究で志望業界の未来を予想する
- OB・OG訪問で社会人のリアルな声を聞く
- インターンで実際の現場を体験する
将来像を描くためには、さまざまな角度から自分自身のキャリア像を明確にする必要があります。しかし、漠然と「社会人としてどのような姿を目指したいと考えているか」と言われても、すぐには答えられない人も多いでしょう。
ここからは、自分の価値観や労働観とマッチした将来像を描くための準備について、4つのアプローチ方法を解説します。ぜひ参考にして、取り掛かれそうなところからチャレンジしてみてくださいね。
①自己分析で将来どうしたいか掘り下げる
自己分析は、就職活動を始める際に真っ先に取り組んでおきたいものです。自分の価値観や強み、興味関心などを理解することで、目指すべき方向性が明らかになってくるでしょう。
自己分析にはさまざまな手法がありますが、この記事では将来像を描くために特に効果的な手法を5種類紹介します。「これならやりやすそうだな」と思ったものから、ぜひ取り組んでみましょう。
自分史を使って過去を振り返る

自分史を活用すると、これまでの人生で経験してきた「やりがいを感じたこと」「困難を乗り越えたエピソード」「自分らしさを発揮できた場面」などについて、時系列で整理できます。
小学校、中学校、高校、大学と、時期ごとに自分の経験について振り返り、どんどん書き出してみましょう。自分がどういう出来事に対して喜びを感じるのか、どんなときに頑張れるのかを思い出すことが、この先の姿をイメージするときのヒントにつながります。
自分史は、紙とペンがあればすぐに取り掛かれる、最も手軽で基本的な自己分析の手法なので、ぜひ一度やってみてください。
他己分析で客観的な評価を聞く

家族や友人、アルバイト先の人などに自分の印象を尋ねることを「他己分析」と言います。どんな人にも、本人だけが気付いていない一面が、長所から短所まで幅広く存在するものです。
「普段の行動」「周囲とのかかわり方」「仕事やプロジェクトへの取り組み姿勢」など、具体的な場面を想定しながら詳しく意見をもらうと、より実践的な気付きを得られるでしょう。
対話をしてから自分自身で将来について改めて考えるのも効果的ですが、そのまま相手に「自分は将来どうなっていると思うか」と質問してしまうのも有効です。
ポイントは、年代や関係性の異なるさまざまな人から意見を聞くことです。たとえば「友人からは協調性があると評価される一方で、上司からはもう少し自分の意見を出してほしいと言われる」といったように、自分の特徴をより立体的に理解できますよ。
他己分析については以下の記事でより詳しく解説しています。
SWOT分析で判断材料を増やす

SWOT分析とは、自分の性格や特徴について多面的に整理していく手法です。「強み」「弱み」「機会」「脅威」という4つの観点から、理想の将来に向けて、自分の立ち位置を客観的に把握できます。
強み(Strength:自分の中にあるプラスの要素)の例
- サークルでのイベント運営を通じて培った企画力がある
- アルバイトで接客経験が豊富
- チームでの活動経験が多く、協調性には自信がある
弱み(Weakness:自分の中にあるマイナスの要素)の例
- プレゼンテーションが苦手
- 専門的な資格を持っていない
- 自分から積極的に意見を発信することが少ない
機会(Opportunity:外部環境の中のプラスの要素)例
- デジタル化の進展でIT知識を持つ人材のニーズが高まっている
- インターンが充実している企業が増えている
- 就活支援サービスが充実しており、情報収集がしやすい
脅威(Threat:外部環境の中のマイナスの要素)の例
- 志望業界の採用人数が減少傾向にある
- 英語力を重視する企業が増えている
- 業界の技術革新が速く、常に新しい知識が求められる
このように自分に関する要素と外部環境の要素を組み合わせて分析することで、理想の将来像に向けて何を活かし、何を改善すべきかが見えてきます。
マインドマップで自分の強みを確認する

マインドマップは、キーワードから連想ゲームのように項目を枝分かれ状に書き足していき、自分の思考を整理するための手法です。「得意なこと」「好きなこと」「苦手なこと」など、自分自身でテーマを設定しながらさまざまなことを書き込んでいけるので、自己理解を深めるのに最適です。
将来を思い描くためには、まずは自分の過去から現在までを振り返り、ここまでの傾向をまとめておく必要があります。
「自分は他の人のために行動するとパワーを発揮しやすい」「一人でコツコツ努力を積み重ねる作業が得意」など、自分の強みを把握したうえで、そこから将来の展望を思い描いていきましょう。
マインドマップを使った自己分析方法は以下の記事でより詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね。
キャリアアンカー分析で自分の軸を確かめる
キャリアアンカーとは、米国の組織心理学者エドガー・シャインが提唱した、キャリア選択のための価値観分析の手法です。企業に合わせて自分を成長させるのではなく、自分自身がもともと持っている価値観や欲求を、キャリア選択の軸に据えようという考え方から誕生したと言われます。
キャリアアンカーを考える基準
- 動機:自分はどんな仕事をしたいのか
- コンピタンス:自分は何が得意なのか
- 価値観:自分は何に意味や価値を感じるか
このような3つの要素を分析し、以下の8つのタイプの中でどれに当てはまるかをチェックします。
キャリアアンカーの8タイプ
- 技能・職能:高いスキルを持ち専門性を高めたいタイプ
- 管理能力:組織の戦略を考えるのが得意な経営者タイプ
- 自律・独立:自分自身のペースで仕事を進めたいタイプ
- 保障・安定:経済的な安定や組織内での安全を優先するタイプ
- 起業家的創造性:新しいアイデアを実現したいと考えるタイプ
- 奉仕・社会貢献:世の中に役立つ仕事をしたいと考えるタイプ
- 純粋な挑戦:困難を乗り越えることに喜びを覚えるタイプ
- ライフスタイル:ワークライフバランスを重視するタイプ
将来像を考えるときに、自分がどのタイプに当てはまるのかをイメージすることで、スムーズに考えられるようになります。書籍などで本格的に分析することも可能ですが、まずはWeb上で受けられる無料診断を試してみるのがおすすめです。
将来像を固めるためにおすすめの自己分析は?

将来像をイメージするための、自己分析のコツを教えてください!

まず、漠然とした状態でも構わないので、自分がどのような働き方をしていきたいのか、自身の興味関心の方向性を考えてみるのが良いと思います。そこから具体的に、自分の理想を実現できる環境を考えていく感じです。

自分自身について理解できても、業界や職種についての知識がなかったら、分析結果をうまく活用できません。よりしっかりした将来像をイメージするためには、自分と社会の両方に目を向けて、自身の中の選択肢を増やすよう心掛けることが重要だと思います。

自己分析はとても重要だと思います。自分の強みを活かした働き方のビジョンを思い描きながら、将来像を考えていくのが良いと思います。

自分史を振り返ってみるのがおすすめです。過去どのようなときに頑張れたのか、成功するパターンは何か、逆にうまくいかないときの特徴など、自分自身の傾向を掘り下げていくと、自分の強みや弱みも浮き彫りになってきます。そこからどんな将来を歩むのが最適かも見えてくるはずです。
②業界研究で志望業界の未来を予想する
将来像を考える際には、自分のやりたいことやなりたい姿だけをイメージしているだけでは不十分です。明確なビジョンを描くためには、志望している業界の動向を把握し、今後どのように変わっていくのかという知識も必要となるでしょう。
未来を完全に予想するのは不可能ですが、せめて現状や数年後の展望くらいまでは、業界ニュースなどの情報に基づいて整理し、考えておくのがおすすめです。
③OB・OG訪問で社会人のリアルな声を聞く
将来のキャリアパスを具体的にイメージするには、実際に活躍している社会人と話してみるのが最も効果的です。OB・OG訪問では、気になる企業で実際に働いている先輩たちからリアルな体験談を聞くことができます。
入社後の成長プロセスや、キャリアの転機となった出来事など、気になることは率直に質問してみましょう。同じ企業で働いていても、その歩み方は人によって異なるので、できれば複数の意見を集められるのが理想です。
リアルな将来像を思い描くために、OB・OG訪問はぜひ積極的に活用しましょう。
OB・OG訪問のメリットを教えて!

OB・OG訪問は、将来像を考えるうえでどのように役立ちましたか?

OB・OG訪問の担当者から、その人自身のキャリアプランに関する話を聞くうちに「ここでなら、私も自分の成し遂げたい未来を実現できそうだな」と確信を持てた経験があります。

担当者の方が実際にどのようなキャリアを歩んできたのか、どんな部署に所属していたのかを聞いて、自分が将来的にどんな仕事に携わりたいのか具体的に考えられるようになりました。また、私生活についても聞けたので、将来像をリアルに想像しやすかったです。

OB・OG訪問で働くうえでのリアルな話を聞くことで、実務への解像度が上がりました。また、先輩方のキャリアプランを聞くことで、自分自身の長期的なキャリアイメージも具体的に描けるようになりました。
「今までOB・OG訪問の経験がなくて、何を聞いたらいいかわからない……」と困っている人には、こちらの記事がおすすめです。
④インターンで実際の現場を体験する
将来のキャリアビジョンを描くうえで、インターンでの実体験は非常に価値の高い判断材料となります。インターネットや書籍で調べるだけではわからないような、職場の雰囲気や実際の業務に直接触れることで、自分が目指すべき将来像がより鮮明になるでしょう。
インターンでは、若手社員やリーダーの働き方を実際に観察できるのが大きな魅力です。また、その企業が持つ判断基準や価値観、文化なども、実際に体感できます。
また、実際に行動してみることで自分の得手不得手もはっきりします。「興味のある作業だったがやってみたら苦手だった」「関心のない業務だと思っていたがやってみたら楽しかった」など、インターンで抱いたさまざまな感想をもとに、将来像をより明確にしていきましょう。
インターンに参加するメリットを教えて!

将来像を考えるうえで、インターンでの経験は役に立ちましたか?

インターンを経験すると良くも悪くも現実が見えてくるので、自分の思い描いているビジョンの中で実現できそうな点とそうでない点が明確になったと感じています。

インターンのグループワークで、実際の業務をオンラインシミュレーションで体験するという活動をしました。その仕事の細部まで知ることができて、将来像をイメージするのに役立ちました。

長期インターンで実務を経験することで、「この仕事は自分には合わない」と実感し、志望業界・職種の選択肢から消すことがありました。
自分の◯年後はどうなる? 時期別・実践的な将来像の描き方
「将来像」と言われても、これから就職活動をしようという段階で「最終的にこうなりたい」という姿をイメージするのは難しいという人も多いでしょう。仕事というものには、実際にやってみるまでわからない要素も多いので、それ自体はいたって自然なことです。
そこで、まずは面接でもよく質問される「3年後、5年後、10年後」というスパンで、自分自身のキャリアを思い描いてみましょう。ここから一般的な例を紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
①入社3年目まで|若手社員としての姿
入社から3年目ごろまでは、プロフェッショナルとしての基礎を確立するための重要な成長期間です。業務の基本を学びながら、組織の一員としての役割を理解し、成果の出し方を覚えていく段階だと言えるでしょう。
初めのうちは、とにかく与えられた業務を着実にこなしていくことが求められます。一通りの業務を覚えて「独り立ち」してからは、徐々に自分なりの工夫や改善を加えていくこともできるようになっていくでしょう。
よくあるパターンとしては、初年度には年間の業務の流れを体験しながら学び、2年目には効率化や品質向上に取り組み始め、3年目になると後輩の指導や新規プロジェクトのサポートに入り始めるといったものが見られます。
自分自身が若手でいる間にも、上司や先輩社員がさまざまな道へと進む姿を見ているはずです。自分はどのような方向に成長していきたいと感じるのか、ときどき整理しながら業務に打ち込むと良いでしょう。
②入社5年後|中堅社員としての姿
入社5年目ごろには、チームの中核メンバーとしての活躍が期待されるようになります。「新人」として扱われることはほぼなくなり、一人前のメンバーとしての自覚と責任感が求められる時期です。
この頃には、自分の専門分野に関するスキルを確かなものにしつつ、関連する領域への理解も広げていく必要があります。たとえば営業職であれば、商品知識や業界の動向に加え、マーケティングの視点や財務の基礎知識も身に付けていくことで、より戦略的な提案をおこなえるようになるでしょう。
また、自身の業務適性も見えてきたこの頃には、今後のキャリアについてもある程度意向が固まっているはずです。
ジェネラリストとして幅広い業務に携わり、いずれは部署を束ねるリーダーになりたいのか。あるいは専門性をとことん高めてスペシャリストの道を歩みたいと思うのか。業務を通して別の事業に興味を持つようになったという人もいるかもしれません。
「将来出世した方がいいのかな」「出世なんてしたくないんだけど、その場合のキャリアはどうなるんだろう」と不安を抱えている人には、こちらの記事がおすすめです。出世に不安を抱える人の体験談や、ほかの道を選んだ場合の選択肢について詳しく解説していますよ。
③入社10年後|リーダーとしての姿
キャリアの転換期となる10年目ごろには、組織やプロジェクトを導くリーダーとしての役割もかなり現実的に視野に入ってくるでしょう。自身の専門性をさらに高めつつも、部下の育成やチームビルディング、事業戦略の立案など、組織全体を見ながら行動する場面が多くなってきます。
この時期には、組織への貢献と自己実現のバランスを取りながら、自分らしい働き方を模索することが重要です。社内でリーダーとしてメンバーを束ねている人もいれば、ステップアップのために新たな環境へと飛び込んでいる人もいます。中には独立して完全に新しいチームのトップとして活躍している人もいるでしょう。
いずれにせよ、自分の強みを最大限活かせる場所や形を柔軟に選択し、より大きな価値を生み出していこうとする姿勢が最も重要です。
ライフイベントを踏まえた現実的なプランを考えるコツ
キャリアプランを考える際には、結婚や出産、転居といったライフイベントも重要な要素となります。たとえば、育児と仕事の両立を見据えて早めにマネジメントスキルを磨く、あるいは専門性を高めて働き方の選択肢を増やすなど、柔軟に考えてみることが重要です。
ライフイベントを踏まえたキャリア戦略の例
- 営業職で培った接触力と人脈を活かして出産後は企画部門に異動する
- 技術職として働きながらマネジメントも学びリモート対応可能なPM(プロジェクトマネージャー)を目指す
- マーケティングの実務経験を積み上げてフリーランスのマーケターとして独立する
このように、ライフイベントを新たな道へ進むきっかけとして捉えることで、より柔軟で充実したキャリアプランを描けるようになりますよ。
将来像を思い描く際に、ライフイベントについてはどれくらい意識した?

私は社会に出るのが少し遅れたため、10年後を描くとライフイベントと仕事の折り合いが悪いと感じていました。そのため、5年で実現したい目標を3年で達成したいくらいの意気込みで、自己研鑽に励もうと考えています。
キャリアばかりを優先してライフイベントをおざなりにしたくはないので、結婚や出産などはしっかり考慮しています。しかし、いろいろなことを気にしすぎては本末転倒です。目の前のことを精一杯頑張った結果として自然とライフイベントがついてくるくらいの感覚で将来を描いています。

就活時から、親元を離れて自分の家庭を持ちたいという強い思いがありました。そのため、将来像を描く際には、一人暮らしや結婚、出産のタイミングなどをかなり具体的に考慮している方だと思います。
その明確なビジョンが原動力となり、新卒で入社した営業職で多くの契約を獲得することができました。その結果実際に、周囲と比べて良好な収入を得ることができ、予定通りに一人暮らしを始め、結婚し、子供を持つことができています。

20代のうちに結婚したいと考えていたため、最初の3~4年は貯金をしつつ、昇進や昇給がしやすいようさまざまなスキルアップを意識して働いています。また、30代での育児休暇取得や子育てとの両立を見据えて、フリーランスになることも目指していました。
しかし現時点で既にライフプランは予定通りには進んでいないため、あまりこだわり過ぎないようにしています。その時々の出会いと縁を大切にしながら、やりたいことを優先して、自分のペースで将来の目標を実現していけばいいと考えています。
面接官も納得! 自分の将来像をわかりやすく伝える構成5ステップ
- 印象に残りやすいシンプルな将来像を述べる
- その姿を目指している理由を述べる
- 何年後にどうなっていたいかを段階的に説明する
- 目標へ向けた具体的な成長プランを伝える
- 企業の未来像との整合性を意識しながらまとめる
面接で将来像について述べるときには、内容の説得力を高める構成の工夫も必要です。ここからは、面接官に良い印象を残せる構成の作り方を5つのステップに分けて紹介します。
企業のビジョンと自己実現をバランス良く関連付けながら、自分ならではのプランを効果的に伝えましょう。
①印象に残りやすいシンプルな将来像を述べる
将来像について質問されたら、まずは自分が目指す将来の姿を端的に表現し、結論から伝えましょう。
たとえば「お客様の課題解決に寄り添える営業担当」「技術を通じて社会に貢献できるエンジニア」といった表現が考えられます。
重要なのは、自分の強みや価値観を素直に反映させることです。華々しい理想論ではなく、着実に成長していける具体的な姿を示すことで、面接官の共感を引き出せるでしょう。また、その企業でこそ実現できる未来像であるかどうかも意識すると、より効果的な回答を考えられますよ。
②その姿を目指している理由を述べる
将来像を述べたら、次にその姿を掲げた理由を説明します。単に「興味があるから」「やってみたいから」だけでは説得力に欠けるため、これまでの経験や価値観と結び付けながら説明することが重要です。
たとえば「学生時代に接客業のアルバイトを経験し、お客様の笑顔に大きなやりがいを感じたので、より深いレベルで課題解決にかかわりたいと考えるようになった」のように、この後のエピソードの概要に触れながら伝えることで、面接官にも思いが伝わりやすくなります。
この部分をしっかり考えておけば、志望動機や入社後に取り組みたいこととも一貫性のある内容にできるので、説得力のある理由を考えるよう心掛けておきましょう。
③何年後にどうなっていたいかを段階的に説明する
続いて、入社後のキャリアの成長イメージを、時期ごとに簡潔に説明します。まずは3年後、次に5年後、そして10年後と、徐々にステップアップしていく姿を示しましょう。
ポイントは、自分が組織にどのように貢献できるようになりたいのかを、具体的に述べることです。
たとえば「チームを率いるリーダーになりたい」のように役職メインで説明してしまうと、自分が出世したいという欲だけが強調されてしまいます。「◯◯という形で会社の利益に貢献できるリーダーになりたい」といった表現を使うのがおすすめです。
会社説明会で知ったことやインターンでの経験も踏まえながら、その企業だからこそ実現したい将来像を簡潔に伝えましょう。
④目標へ向けた具体的な成長プランを伝える
さらに、目標達成に向けて入社1~2年目の間にどのような努力をしたいと考えているかも述べましょう。
ポイントは、具体的な行動と期待される成果を結び付けて説明することです。たとえば「毎週の勉強会に参加して専門知識を深める」「先輩の商談に同行し、実践的なスキルを学ぶ」など、行動レベルまで落とし込んだ計画を示すことで、あなたの成長意欲と実行力が伝わりますよ。
企業が提供する研修プログラムについても触れながら、自己成長への具体的なコミットメントを示すと良いでしょう。
⑤企業の未来像との整合性を意識しながらまとめる
最後に、自分の将来像と企業の目指す方向性との関連性についても触れると良いでしょう。
たとえば、IT企業であれば「デジタル技術を活用して社会問題の解決に貢献したい」という自身の思いと、志望先企業の「技術の力で人々の暮らしを豊かにする」というビジョンが合致しているといった例が考えられます。
また、自分自身の成長が、企業の発展にどのようにつながるのかについても述べられるとさらに良い回答になります。「新規事業の立ち上げにも携わり、会社の次世代の柱を作り出すことにも貢献したい」のような表現が望ましいです。
ただし、無理やりこじつけるような内容にならないよう注意は必要です。企業によっては、調べてもこの先の事業の展望がわからない場合もあるでしょう。そういったときには自分の成長意欲をメインでまとめ、回答を終わらせても構いません。
どんなキャリアが王道? 8大業界の一般的なキャリアパスと回答例8選
「何年後のキャリアを考えようと言われても、そもそも実際にどんなパターンがあるのかわからない……」
「自分の志望している業界ではどのようなステップアップをする例が一般的なのか」
このような疑問を抱く人は多いでしょう。その業界で働いたことがない以上、こう思うのはまったくおかしなことではありません。
ここからは、業界別に一般的なキャリアパスの例と、それに沿った「将来像」の回答例を紹介します。企業によってどのようなキャリアが歩めるのかは異なりますが、自分の目指している業界が含まれている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
①メーカー
メーカーでは通常、入社後は研究開発や製造現場で基礎力を養います。その後、製品開発プロジェクトでの経験を重ね、チームマネジメントへと活躍の場を広げていきます。中堅社員になると、より大きな視点での新製品の戦略プランにも携わるようになっていきます。
例文
私は、技術と人をつなぎ、社会にイノベーションをもたらすエンジニアを目指したいと考えています。
こう考えるようになったきっかけは、大学での研究室活動です。チームで新技術の開発に取り組む中で、技術の可能性を追求することのおもしろさと、それを実用化することの重要性を実感しました。
入社後3年間は製品開発の現場で技術力を磨き、5年後にはプロジェクトリーダーとして新製品開発を担当させていただきたいと考えています。そして10年後には、次世代製品の開発責任者として、市場ニーズと技術を結び付けた製品企画ができる人材に成長したいと思います。
そのために入社後は、技術研究会への参加や資格取得にも計画的に取り組んでいく所存です。御社の「技術を通じて人々の暮らしを豊かにする」という理念に共感しており、私も製品開発を通じて社会に貢献していきたいと考えています。
この回答例のポイントは、技術者としての専門性の追求と、組織での価値創造という両面のバランスが取れている点です。また、具体的な成長プロセスを示しながら、企業理念との結びつきまで意識した構成となっています。
②商社
商社では入社後、特定の商材を担当しながら商取引の基礎を学びます。中堅社員になると新規開拓やチームマネジメントを任されるようになり、経験を重ねた後は新規事業の立ち上げなど、より大きな視点での仕事に携わるパターンが一般的です。
例文
私は、国内外のビジネスを通じて新しい価値を創造できる人材を目指しています。
この目標を持つきっかけとなったのは、大学のゼミで取り組んだ貿易実務の研究です。日本企業の海外展開における課題を学ぶ中で、グローバルなビジネス創造に強い関心を持ちました。
入社後3年間は商材の知識と商取引の基本を着実に身に付け、5年後には新規市場の開拓にも挑戦したいと考えています。そして10年後には、海外事業の企画立案を担当し、新しいビジネスモデルを提案できる存在になりたいと思います。
そのために日々の英語学習に加え、入社後は御社の研修制度を積極的に活用させていただきたいと考えています。御社が掲げる「企業と企業を結び、新たな価値を創造する」という理念に共感しており、私もその実現に貢献していきたいと思います。
この回答例の強みは、自身の経験に基づく明確な志望動機と、具体的な成長イメージをわかりやすく示している点です。また、入社前からの準備姿勢にも触れることで、目標達成への意欲と実行力が伝わる内容となっています。
商社を志望している人は、こちらの記事で志望動機の書き方も学んでおきましょう。
③小売
小売業では、まず店舗での実践を通して接客や売場づくりの基礎を学びます。その経験を活かして店長として店舗運営の責任を担い、さらに経験を重ねることでエリアマネージャーや、本部での商品企画など、より幅広い視点での仕事に携わっていく例が一般的です。
例文
私は、お客様の日々の暮らしに寄り添える店舗づくりのできる人材を目指しています。
こう考えるようになったきっかけは、大学生活3年間続けた食品スーパーでのアルバイトです。お客様の声に耳を傾け、売場づくりを工夫する中で、小売業の持つ地域密着型のサービス創造に魅力を感じました。
入社後3年間は店舗での実務経験を通じて現場力を磨き、5年後には店長として自分なりの店舗運営に挑戦したいと思います。10年後にはエリアマネージャーとして、地域特性を活かした店舗づくりを実現できる存在になることを目指しています。
そのために入社までに、アルバイトで得た経験を体系的に整理し、御社の研修ではお客様視点でのサービス提供について深く学ばせていただきたいと考えています。御社の「地域に根ざした店舗へ」という理念に共感しており、私もその実現に力を尽くしていきたいと思います。
この回答例のポイントは、アルバイト経験を通じて培った現場感覚と将来のビジョンを効果的に結び付けている点です。特に地域密着型の店舗づくりという具体的な目標は、小売業ならではの魅力を理解していることが伝わってきます。
④金融
金融業界での仕事は、支店での窓口業務や営業活動を通して基礎的なスキルを磨くところからスタートします。その後、個人営業や法人営業など得意分野を確立し、支店長や本部スタッフとして、より大きな視野でビジネスにかかわっていくのが一般的なキャリアの歩み方です。
例文
私は、お客様一人ひとりに最適な金融サービスを提案できるプロフェッショナルを目指しています。
きっかけは、ゼミでの金融教育プロジェクトです。地域の方々への家計管理セミナーの企画運営に携わる中で、金融リテラシーを活かした社会貢献に興味を持ちました。
入社後3年間は窓口業務と営業活動を通じて基礎力を養い、5年後には個人営業のリーダーとして成果を上げたいと考えています。10年後には支店の中核として、地域のお客様の資産形成に貢献できる存在になることが目標です。
入社までに金融の基礎知識を深め、御社の研修では実践的なスキルを吸収していきたいと思います。御社の「金融でお客様の生活をより豊かで安心なものに」という方針に共感しており、私もその実現に尽力したいと考えています。
この例文の良さは、金融教育という社会性のある活動経験から、仕事への意欲と将来像を導き出している点にあります。また、資産形成支援という具体的な目標設定により、顧客志向の姿勢が感じられる内容となっています。
⑤広告・出版・マスコミ
広告・出版・マスコミ業界では、入社後しばらくは先輩社員の下で企画や制作の基本を学びます。その後、自身でプロジェクトを任されるようになり、チームリーダーとして大型案件を手掛けたり、新規事業の立ち上げに挑戦したりと、創造的な仕事の幅を広げていくことができます。
例文
私は、時代の変化を捉えながら、心に響くコンテンツを創り出せるクリエイターを目指しています。
こう考えるようになったきっかけは、大学の広告研究会での活動です。地域の小規模店舗のSNS発信を手伝う中で、誰かの想いを形にして届けることの難しさと喜びを実感しました。
入社後3年間は企画制作の現場で基礎を学び、5年後にはチームリーダーとして自分たちならではの企画を提案できるようになりたいと考えています。10年後には、新規プロジェクトの責任者として、社会の課題に向き合うような新しいコンテンツを生み出せる存在を目指したいと思います。
そのために日頃からさまざまな映像や広告作品に触れ、制作者の意図を考察する習慣をつけています。御社の掲げる「心に響くコンテンツづくり」という理念に共感しており、私も新しい表現の可能性に挑戦していきたいと思います。
この回答例の良い点は、クリエイティブへの真摯な姿勢と、表現者としての成長意欲が自然な形で表れている点です。特に、日常的な作品分析という具体的な取り組みに触れることで、創造性を磨く意識の高さが伝わってきます。
⑥IT・通信
IT・通信業界では、まずは開発やサービス運用の現場でスキルを磨きます。その後、プロジェクトマネージャーとしてチームを率い、さらにプロダクトマネージャーや事業責任者として、サービス全体の成長を担う立場へとステップアップしていくケースが一般的でしょう。
例文
私はテクノロジーを活用して、人々の生活をより便利で豊かにできるエンジニアを目指しています。
大学でのプログラミングサークル活動が、この目標を持つようになったきっかけです。メンバーと協力してアプリ開発に取り組む中で、技術で人々の課題を解決することにやりがいを感じました。
入社後3年間は開発現場で技術力を磨き、5年後にはプロジェクトリーダーとして新サービスの立ち上げに携わりたいと考えています。10年後には、プロダクトマネージャーとして、ユーザーニーズを捉えた新しいサービスを生み出せる存在になることが目標です。
そのために、現在は技術ブログの執筆を通じて最新技術のキャッチアップを心掛けています。御社の「テクノロジーで未来を創る」という方針に共感しており、私も技術の力で社会に貢献していきたいと考えています。
この回答例は、技術への情熱とビジネス視点のバランスが取れている点が特徴です。具体的な経験に基づく動機付けと、段階的な成長イメージの提示により、実現可能性の高い将来像として説得力があります。
IT業界を志望している人は、こちらの志望動機に関する記事も読んでみましょう。
⑦サービス・インフラ
サービス・インフラ業界では、現場での実務経験を通じてサービスの基本を学びます。その後、エリアマネージャーとして複数拠点の運営に携わり、さらに本部での企画立案や新規事業開発など、より広い視野での仕事にチャレンジする機会が増えていきます。
例文
私は、安心・安全なサービスを通じて、地域社会の発展に貢献できる人材を目指しています。
この思いを抱くようになったのは、大学での地域活性化プロジェクトがきっかけです。地域の方々と接する中で、インフラサービスが街の暮らしを支える重要な存在だと実感しました。
入社後3年間は現場でサービスの基礎を学び、5年後にはエリアマネージャーとして地域特性を活かした運営に携わりたいと思います。10年後には、本部で新規サービスの企画開発を担当し、社会のニーズに応える新しい価値を提案できる存在になることが目標です。
そのために、さまざまな地域のインフラ整備事例を調べ、実際に現地へ足を運んで学ぶ機会を作っています。御社の「地域とともに成長する」という理念に共感しており、私も社会貢献を実現していきたいと思います。
この回答は、フィールドワークを通じた主体的な学びの姿勢が説得力につながっています。特に、実際に現地へ足を運ぶという具体的な行動が、業界への深い関心を示しています。
⑧官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体では、まず各部署での実務を通じて行政サービスの基礎を学びます。その後、主任、係長、課長補佐といった役職に就き、さらに課長として政策立案や組織運営の中核を担うなど、より広い視野での仕事に携わっていきます。
例文
私は、市民の視点に立って社会課題の解決に取り組める公務員を目指しています。
この目標は、大学でのボランティア活動を通じて芽生えました。子ども食堂の運営支援にかかわる中で、行政サービスが果たす役割の重要性を実感しました。
入社後3年間は現場で実務経験を積み、5年後には主任、10年後には係長として地域の実情に即した施策を推進し、市民生活の向上に貢献できる存在になることが目標です。
そのために普段から地域の集会や市民活動に参加し、実際に住民の方々の声に耳を傾ける機会を大切にしています。御庁の「市民に寄り添う行政サービス」という理念に共感しており、私も住民目線でのサービス向上に尽力していきたいと考えています。
この回答例の魅力は、机上の空論ではなく、実際の地域活動を通じた学びを重視している点です。特に、住民との直接的な対話を心掛けているという具体的な行動が、公務員としての基本姿勢への理解を示しています。
職種別! 「将来像」を効果的に伝える回答例7選
業界だけでなく、職種によっても求められる将来像は異なってきます。ここからは、それぞれの職種ならではの専門性や成長プロセスを意識した回答例を紹介します。
先輩たちが現場で見ている実際のキャリアの歩み方も併せて紹介するので、自分の志望職種に合わせて、自分らしい将来像を描く際の参考にしてみてくださいね。
①営業職
営業職は、企業の商品やサービスの特徴を理解し、顧客にその価値を伝えることで信頼関係を築く役割を担います。入社当初は基礎的な営業スキルや商品知識を身に付けながら、小規模な案件を通して経験を積むケースが一般的です。さらにキャリアを重ねると、大型取引を任されたり、営業戦略の策定やチームのマネジメントを担当する機会が増えていきます。
例文
私は、顧客の課題を解決し、その成長を支える営業担当者を目指しています。
大学時代、学園祭の運営で地元企業に協賛を依頼する活動をおこない、企業のニーズを理解しながら信頼を得る大切さを学びました。この経験を通じて、営業という仕事に興味を持つようになりました。
入社後3年間は、商品知識や業界について深く学び、小規模な案件で実績を積むことで実務スキルを磨きたいと考えています。5年後には主要顧客を担当し、10年後には新規市場の開拓やチームリーダーとして活躍したいと考えています。
御社は、革新的な提案を通じてお客様と共に成長することを理念に掲げ、地域社会からも厚い信頼を得ています。私はその一員として、これまでの経験と努力を最大限活かし、御社の成長に貢献したいと強く願っています。
現在、業界の動向を把握するためにニュースやセミナーを積極的に活用して知識を深めています。御社の掲げる「顧客と共に成長する」という理念に共感しており、その実現に貢献したいと考えています。
この例文では、具体的な経験を交えながら営業職への適性と意欲を伝えています。また、将来の成長計画を段階的に示し、企業の理念と結び付けることで説得力を高めています。
就活生・現役社会人に聞く営業職の将来像

あなたの知っている、営業職の将来像の例を教えてください!

営業職の場合、入社後5年くらいすると「そのまま営業一筋でいくのか」「本社などに戻りバックオフィスも担当するようになるのか」という2種類に分かれていくことが多いようです。

成績が良い先輩は楽しく仕事していますが、成績が悪い先輩は大変苦労していると感じます。そういう意味で、営業職は向き不向きがはっきりしている職種だなと思います。

私の勤務先は人材系なので、営業職を数年勤めた後で人事に転向するケースが多いです。ほかの会社に転職して人事になるパターンか、今の会社でリーダーを目指すのかという2択が一般的だと思います。
営業職を目指している人には、こちらの志望動機に関する記事もおすすめです。実際に営業職の内定を勝ち取った先輩の体験談とともに、業界別の例文を多数紹介しています。
②技術職
技術職は、製品開発や設計の基礎を学びながら、専門知識やスキルを深めていく職種です。入社当初は既存製品や部品の改良に取り組み、徐々に新製品開発やプロジェクトの中核を担う役割へと進んでいきます。さらにキャリアを積めば、部門を統括する技術責任者や業界をリードする専門家として活躍する道が開けていくでしょう。
例文
私は、高品質な製品を通じて社会に貢献する技術者を目指しています。
大学では、自動車部品の耐久試験をテーマに研究をおこない、製品の安全性が細部へのこだわりによって支えられていることを学びました。この経験を通じて、技術者としての責任感が芽生えました。
入社後3年間は、設計や品質管理の基礎を学び、製品開発プロセス全体への理解を深めたいと考えています。5年後には新製品開発の中核メンバーとして活躍し、10年後には技術革新を推進するリーダーを目指しています。
御社は「世界に誇れる品質」を追求し、多くの人々の生活を支える製品を提供してきました。この理念に共感するとともに、御社の製品をさらに進化させるお手伝いができればと強く思っています。
現在、CAD資格の取得に向けた学習や、材料工学の最新動向を調べる努力を続けています。御社の「品質へのこだわり」に共感しており、私も技術を通じて社会に貢献したいと考えています。
この例文では、大学での研究活動を起点に技術職への志望動機を明確に伝えています。また、将来の目標を具体的に示すことで、説得力のある内容となっています。
就活生・現役社会人に聞く技術職の将来像

あなたの知っている、技術職の将来像の例を教えてください!

入社して何年かすると、そのまま技術を磨いてスペシャリストになるのか、ほかの仕事もできるジェネラリストの道を進むのかを選ぶ必要が出てくるようです。たとえば技術的な知識を活かして、今では営業としてバリバリ活躍している人がいました。

エンジニアとして働いています。入社後3~5年の間にも少しずつポジションが上がっていき、その後はシニアエンジニアとして活躍するケースが一般的だと思います。その後はマネージャー、ディレクター、あるいはプリンシパルエンジニアといったポジションに進むことが多いようです。
③企画職
企画職は、市場調査やアイデアの具体化を通じて企業の成長を支える役割を担います。入社後は、先輩社員の指導を受けながらプロジェクトを経験し、徐々に事業戦略の立案や新規事業の立ち上げなど、より責任のある業務に携わるようになります。
例文
私は、人々の心に響くアイディアで、価値を届ける企画職を目指しています。
大学時代、地域活性化イベントの企画運営を通じて、自分のアイデアが形になり、多くの人に喜ばれる経験をしました。この経験から、企画の持つ力に魅力を感じ、より広い範囲で価値を届ける仕事がしたいと考えるようになりました。
入社後3年間は市場分析や提案スキルを磨き、5年後には新規プロジェクトを主導する役割を目指しています。そして10年後には、事業戦略の立案に携わり、御社の成長に貢献したいと考えています。
御社の「創造力で未来を切り拓く」という理念に共感し、これまでにない価値を創り出す企画を一緒に実現したいと思っています。御社が手掛けたプロジェクトの成功事例に触れるたび、その先進性に感銘を受け、私もその一員として活躍したいと感じています。
現在、マーケティング関連の書籍を読んだり、成功したプロジェクト事例を分析するなどしてスキル向上に努めています。一刻も早くクリエイティブなアイデアを提供できるよう、今後も勉強していきます。
この例文では、企画に対する情熱を具体的な経験を交えて語り、成長目標を明確に設定しています。また、企業理念への共感を示すことで、志望動機との一貫性も持たせています。
就活生・現役社会人に聞く企画職の将来像

あなたの知っている、企画職の将来像の例を教えてください!

企画職の場合、入社後5年目あたりから転職する人が増えてくるイメージがあります。実際に、内定後のOB・OG訪問のときに、5年後には約3割の人が別の企業に転職していると聞きました。

そのまま企画職としてキャリアを積んで主任や課長になるケースもあれば、別の部署で活躍している人もいて、結構人それぞれです。本人が希望する場合もあれば、スキルの幅を広げるために人事から言われて異動するケースもあるように見えます。
④研究開発職
研究開発職は、基礎研究を通じて新しい知識を得ながら、応用研究や新製品開発に挑む仕事です。入社後の初期段階では、研究チームの一員として課題解決に取り組みます。キャリアが進むにつれて、研究チームを率いるリーダーや業界の技術革新を牽引する存在として活躍することが期待されるようになるでしょう。
例文
私は、新しい技術で社会に変革をもたらす研究者を目指しています。
大学時代、次世代バッテリーの研究に取り組み、試行錯誤の末に得た新しい発見が大きな喜びとなりました。この経験を通じて、実用化を目指した研究開発の道に進む決意を固めました。
御社は、これまでに数多くの革新的な製品を世に送り出してきました。私も御社の一員として、その歴史に新たな1ページを刻むような研究開発に貢献したいと考えています。
御社では、まず3年間で基礎研究を通じてスキルを磨き、5年後には製品化プロジェクトの中心メンバーとして貢献したいと考えています。そして10年後には、新技術の開発を主導し、業界のイノベーションをリードする存在になりたいです。
現在、専門分野の論文を読み込むほか、技術セミナーに参加して知識を深める努力を続けています。御社の「技術で未来を創る」というビジョンに共感しており、その実現に貢献したいと考えています。
この例文では、研究経験をもとに研究開発職への適性と目標を具体的に伝えています。また、計画的な成長プロセスを示し、志望動機と結び付けることで説得力を持たせています。
就活生・現役社会人に聞く研究開発職の将来像

あなたの知っている、研究開発職の将来像の例を教えてください!

キャリアアップを図る場合には、企業の研究職で数年働いてから、省庁の研究職に転職する方や自社で管理職として昇進するケースが多いと聞いたことがあります。
⑤マーケティング職
マーケティング職は、商品やサービスを顧客に効果的に届けるための戦略を立案し実行する仕事です。入社後は、データ分析や市場調査を基礎とした広告運用やプロモーション活動を経験します。経験を積むことで、次第にさらに高度なマーケティング戦略の設計やブランド構築プロジェクトに携わる機会が増えていきます。
例文
私は、データに基づいたマーケティング戦略で顧客の心を動かし、御社のブランド価値を高める役割を担いたいと考えています。
大学時代、ゼミ活動の一環として地域特産品の販売促進プロジェクトに参加し、データ分析を活用したSNSキャンペーンを企画しました。この取り組みで売上が前年比120%を記録し、マーケティングの力で成果を生み出せる喜びを実感しました。
御社のマーケティングチームは、デジタル分野における革新的なアプローチで業界をリードしています。そのような環境で、まず3年間は市場分析や広告運用を通じて基礎を固め、5年後にはキャンペーンのリーダーとして新規顧客の獲得に貢献したいと考えています。そして10年後には、ブランド戦略の設計を手掛け、御社で価値ある成果を生み出せる存在を目指していきます。
現在も、最新のマーケティング手法を学ぶためにウェビナーや専門書を活用し、実践的な知識を身に付けています。御社で価値ある成果を生み出せるように、努力を続けていきたいです。
この例文では、学生時代の経験をもとにマーケティング職への興味と適性を伝えています。また、具体的なキャリアプランを示すことで実現可能性の高さをアピールし、企業の理念に対する共感をしっかりと表現しています。
就活生・現役社会人に聞くマーケティング職の将来像

あなたの知っている、マーケティング職の将来像の例を教えてください!

マーケティング職の場合、ほかの業界や企業にも転用しやすいスキルが身に付くこともあり、3~5年後くらいにはキャリアアップを目指して転職している人が多いと感じます。
⑥コンサルタント職
コンサルタント職は、クライアントが抱える課題を解決し、企業の成長をサポートする仕事です。入社初期はデータ収集や分析、プレゼン資料の作成など基礎的な業務を経験し、徐々にクライアントとの対話やプロジェクトの設計に携わります。最終的には、プロジェクト全体をリードするポジションへと変わっていくでしょう。
例文
私は、データを活用した問題解決と戦略立案でクライアントの成長を支援するコンサルタントを目指しています。
大学のゼミ活動では、実際の企業をモデルにした経営分析をおこない、課題解決案を発表するプロジェクトに参加しました。チームでデータを整理し、具体的な提案を導き出す中で、論理的思考力とコミュニケーションの重要性を学びました。
御社の多様な業界へのコンサルティング実績と、クライアントと深くかかわる姿勢に強く惹かれています。まず3年間は業界知識とコンサルティングスキルを徹底的に学び、5年後にはプロジェクトの中心メンバーとして貢献したいと考えています。そして10年後には、プロジェクト全体を統括し、クライアントのビジョン実現を支え、成果を生み出せる存在を目指していきます。
現在、ケーススタディを通じて課題解決力を養うとともに、御社の過去の成功事例を深く研究しています。御社の「クライアントと共に未来を創る」という理念に強く共感し、その実現に貢献したいと思っています。
この例文では、具体的な経験をもとにコンサルタントへの適性を示しています。また、企業の特徴に触れつつ将来像を描くことで、説得力を持たせています。
就活生・現役社会人に聞くコンサルタント職の将来像

あなたの知っている、コンサルタント職の将来像の例を教えてください!

コンサルタントの場合、バリバリ出世する人と業界から離れてしまう人の二極化が激しいです。順調な人なら、コンサルタントからシニアコンサルタント、マネージャーと順調に昇進していけますが、ついていけずにすぐ辞めてしまう人も多い世界です。

私の周りでは、コンサルタントとして入社後3年で基本的な業務ができるようになり、そのタイミングで事業会社への転職や起業など、次のキャリアステップに進む人が多いです。
⑦事務職
事務職は、企業活動を支える重要な役割を担います。入社当初は、資料作成やデータ入力、問い合わせ対応といった基本業務を担当します。キャリアを重ねると、業務プロセスの改善提案やチーム全体のサポートを通じて、企業の運営効率向上に寄与するポジションが期待されるようになっていきます。
例文
私は、正確で迅速な事務業務を通じて企業の基盤を支える役割を担いたいと考えています。
大学では、学生団体の運営を担当し、イベントの資料作成や参加者の管理をおこないました。特に、効率的な作業フローを設計したことで、従来より短時間で業務を終えることができ、メンバーからの評価も得られました。この経験を通じて、事務職の重要性を実感しました。
御社は、社員全員が安心して働ける環境を整え、成長を支える仕組みを大切にされています。この理念に共感し、まず3年間は正確で丁寧な業務遂行を徹底し、5年後には業務プロセスの改善を提案できる役割を目指したいと考えています。10年後には事務部門のリーダーとしてチーム全体を支え、成果を生み出せる存在を目指していきます。
現在、業務効率化のためのツールを学ぶなど、事務職に必要なスキル向上に努めています。御社の「良い社会を作るためには良い会社から」という理念に共感し、その一翼を担いたいと考えています。
この例文では、学生時代の経験を活かし事務職への適性を示しています。また、具体的なキャリアプランを述べることで将来像が明確になっています。
就活生・現役社会人に聞く事務職の将来像

あなたの知っている、事務職の将来像の例を教えてください!

私が内定を獲得した企業では、事務職のまま3年、5年、10年とキャリアを積み重ねている人が多い印象です。

中には営業職など別の部署に異動している人も見られますが、基本的には、数ある事務の仕事の中から自分の得意分野を見つけ、特定部署での業務を極めている人が多い印象があります。
事務職に興味がある人は、こちらの記事も併せてチェックしてみてくださいね。
将来像はどこまで実現している? 先輩たちの現在の姿を聞いてみた
ここまで将来像の描き方について解説してきましたが、実際に就職した後にそのプランはどれくらい実現するものなのでしょうか。
既に実際に働いている先輩たちに、今の状況を詳しく聞いてみました。あの頃に想像していた道を歩んでいるのか、あるいは途中で方向転換して今は別の道を目指しているのか、じっくりチェックしてみましょう。

「早く親元を離れて、自分の家庭を築きたい」という当初の将来像は、予定通り実現することができました。自動車ディーラーの営業職として入社し、多くの契約を獲得して収入を得たことで、周囲の友人たちよりも早く結婚し、子供を授かることができました。
現在も新たな将来像を設定して努力を続けている最中
その目標を達成したことで、新たな将来像として「お金よりも妻や子供と過ごすプライベートの時間を大切にし、楽しい家庭の思い出を作っていきたい」という思いが生まれました。そこで、土日休みで残業や休日出勤の少ない職場への転職を決意し、現在はワークライフバランスの取れた企業で働きながら、家族との時間を大切にするという新しい将来像に向かって進んでいます。

就職活動時に描いていた将来像とは多少異なるものの、「英語を活用した仕事に就きたい」「プライベートと仕事のバランスが良い環境で働きたい」という軸には沿っていると感じています。入社当初は単調で決まりきった仕事ばかり任され、就職先を間違えたのではないかと思うこともありましたが、2年目となった現在では、ようやく自分がやりたいと考えていた仕事を任せてもらえるようになり、その点では順調です。
今後はよりスキルを磨いて理想の姿に近付いていきたい
一方で、就職活動時には技術的な成長をより速いペースで実現できると期待していたため、エンジニアとしてのキャリアの進展は想像していたよりもゆっくりとしたペースだと感じています。それでも、自分の軸に沿った環境で働けている点には満足しており、エンジニアとして成長したいという将来像は変わっていません。

私の思い描いていた将来像とは大きく変わり、その過程もまったく異なっていますが、根底として目指したいものには順調に進んでいるように感じます。
現在入社4年目で、当初の人生設計ではこの時期に昇進して結婚している想定でしたが、病気による入院なども重なって実現できていません。しかし、趣味の活動で出会った友人と会社を運営することになったり、芸能事務所にスカウトされて俳優活動を始めたり、入院を機にフリーランスサイトに登録して案件を獲得できるようになるなど、さまざまな縁から将来が広がりました。
想定外のアクシデントもパワーに変えて歩み続けている
現在は友人の会社の手伝いを本業とし、副業でWeb系のライティングやSNS運用をおこなって生活する方向に目標をシフトしています。これまで漠然と決めていた設計がより具体的になり、スキルアップのためにはじめた副業で収入が少しずつ上がっていることや、休職を経て本業が融通の利きやすい働き方となって両立がしやすくなったこともあり、その目標に向けて順調に歩みを進めることができています。
要注意! 面接官が評価を下げる4つの回答パターン
面接で「将来像」について答えるときには、表現の方法を誤ると、かえって相手に悪い印象を残してしまう場合もあります。
ここからは、将来像について答える際に注意したい「NG回答例」を4つのカテゴリに分類して紹介します。悪気なく使ってしまいかねないフレーズもありますので、必ず確認しておきましょう。
①自分の成長にしか関心のない回答
面接の場で、自分自身のスキルアップや成長への意欲をアピールすることは重要です。しかし、それだけでは企業に対する貢献意欲が伝わりません。
企業は「応募者がどのように会社の利益に貢献してくれるか」を重視するものです。そのため、自分中心の視点だけではなく、会社やチームへの貢献についても触れる必要があります。
自分の成長にしか関心がない回答の例
- スキルアップして成長していきたいです
- いろいろな経験を通じて自分の市場価値を高めたいです
- どんどん新しいことを吸収してキャリアアップしていきたいです
- たくさんの資格を取得して専門性を身に付けたいです
- さまざまな部署を経験して自分の可能性を広げていきたいです
回答には「自分の成長」だけでなく「その成長を活かしてどう貢献するか」を明確に含めることが重要です。たとえば「市場分析のスキルを高め、データに基づいた提案によって御社の成長に寄与したい」といった形で、自分の成長が会社にとってのメリットにつながることを示しましょう。
②具体性を欠いた抽象的な表現
抽象的でぼんやりとした回答では、面接官に自分の考えがしっかりしていない印象を与えてしまいます。特に「頑張りたい」や「成長したい」という言葉だけでは、何をどのように目指しているのかが伝わりません。具体的な目標や目指す期限、そこへのアプローチ方法まで明確にするよう心掛けましょう。
抽象的な回答の例
- やりがいを感じられる仕事をしていきたいです
- 常に挑戦し続けられる環境で頑張りたいです
- 幅広い経験を積んで成長したいです
- チームで協力して成果を上げていきたいです
- 自分らしく働ける仕事をしたいです
自分の過去の経験をもとにしたエピソードを盛り込んだり、その企業だからこその理念や価値観に触れる内容にしたりといった工夫をすると、具体的な回答を作成できます。ほかの学生と内容が重複しないような、自分だけの回答例を考えるよう心掛けてくださいね。
③業界・企業研究不足の安易な目標
業界や企業に対する理解が不足したまま回答を作ると、どの企業でも通用する「テンプレート」だと見抜かれてしまいます。企業の特徴や理念に触れない抽象的な回答をすると「本当に当社を志望しているのか」という疑念を招きやすいので注意が必要です。
業界・企業研究不足の回答の例
- 社会貢献ができる仕事をしたいです
- 安定した環境で長く働きたいです
- 新しいことに挑戦できる会社で成長したいです
- お客様に喜んでもらえる仕事をしたいです
- やりがいのある仕事がしたいです
面接に臨む前に、志望企業の特徴や業界の課題についてしっかりリサーチしましょう。たとえば「御社が提供する〇〇サービスは地域社会に大きく貢献しているため、私もその一員として価値を広めたい」といった形で、企業独自の取り組みを踏まえた回答を作ることで熱意を伝えることができます。
④実現可能性の低いおおげさな構想
大きな目標や夢を語るのは良いことですが、あまりに現実性に欠ける内容だと「自分の立場を理解していない」と判断されてしまう可能性があります。
実現可能性の低い回答の例
- 入社半年で主任としてプロジェクトを指揮したいです
- 会社全体の戦略を変えるような提案をしていきたいです
- 10年後には社長として会社を引っ張っていきたいです
- すぐに海外事業の責任者になりたいです
- 入社直後から新規事業の立ち上げを任されたいです
目標を段階的に設定し、現実的なプランを示すことで説得力を高めましょう。たとえば「入社から3年間で一通りの業務をこなせるようになり、5年後には新規プロジェクトの中心メンバーとして貢献したい」といった形で、現実的な成長プロセスを示すことが重要です。
将来像を思い描くには準備が必須! 自己理解と業界知識を深めてから未来をイメージしよう
ここまで、将来像に関する質問の攻略法について解説しました。
この質問への回答のコツは、しっかり自己分析をおこない自分の価値観を理解したうえで、志望している業界や企業との関連性を見出すことです。それぞれの業界の一般的なキャリアパスを把握し、その通りに進もうと考えているのか、あるいは独自の道を進んでみたいのかを考えてみましょう。
自分の将来像について考える時間は、楽しいものです。理想の自分を思い描きながら、そこへたどり着く道筋も考え、就活に対するモチベーションを高めていきましょう。

変化が激しいこの世の中で、3年後、5年後といった将来像を描くことはどんどん難しくなっています。皆さんの現在も、3年前、5年前に予想した通りの状況と言えるでしょうか。
これは企業や就活においても同じで、あらゆる業界で「変化する力」「対応力」が求められ、重要度の高いビジネススキルとなっているなかで、就活生に「自分の将来像を明確に語れ」というのはナンセンスでしょう。多くの人事や面接官はそのことに気付いているため、近年はあまり聞かれない傾向にあります。
将来像が明確過ぎると「仕事を”選ぶ”人」という印象に……
それでは、万が一この質問をされたらどう答えるのが正解でしょうか。押さえておくべき点は、あまりに明確に、具体的に「私はこうなっていたい、これをしたい!」と言いすぎると「この人は仕事を”選ぶ”人ではないか」と逆にマイナス評価になる可能性があるということです。
企業全体として変化対応力が求められる環境では、「なんでもやってみたいです!」というオープンマインドがある人は評価が高いです。
そのため、もし回答をするのであれば「新卒として1から仕事を覚える間は、何でも求められたことをやってみたいと思います。ただ、あえて言えば〇〇に興味が強いです」くらいにとどめた切り返しがベストかもしれませんね。
就活力診断テストはもう使いましたか?
「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。
面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。
\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/
診断スタート(無料)
















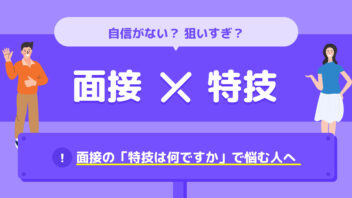



私はライターとして働いています。案件に参画すると、必ずライターを取りまとめるディレクター職の人がいます。ライターとして実績を積んだ先には、このようなプロジェクトを管理する立場の仕事に変わってくるのだと思います。