仕事をサボるのはダメ? 社会人に聞いた上手くサボるコツやバレた時の対処法
「仕事をサボりたいと思っているけど、本当にサボっても良いのかな……」
「ほかの人たちはどうやって仕事をサボっているのだろう」
現在働いている人のなかには、仕事をサボっても問題ないのか、周りに怪しまれずサボる方法はあるのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。上手に仕事をサボるためには、息抜きのタイミングや会社を休むときの伝え方など、さまざまな点でコツが必要です。
この記事では、仕事を上手にサボるコツやバレたときの対処法、サボりたい気持ちを解消するポイントを社会人の体験談も交えて解説します。
仕事で適度に息抜きし、ストレスを軽減して楽しく働き続けたい人は、ぜひ参考にしてください。
| 就活生の5大不安を解決!
オススメのツール5選 |
|
|---|---|
| ツール名 | 特徴 |
| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |
| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |
| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |
| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |
| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |
社会人が実際に「仕事をサボりたくなった」瞬間とは
人によって悩みの種類は異なるものの、仕事のストレスから「サボりたい」と思うのは誰にでもあることです。しかし、多くの人は「自分だけが仕事をサボりたいのかもしれない」と不安になりますよね。
そこで、社会人の先輩たちに「仕事をサボりたい」と思ったことがあるのか、対処法も合わせて聞いてみました。

どんなときに「仕事をサボりたい」と思ったことがありますか?

体調が悪いときや、モチベーションが上がらないときに、上司に相談して気持ちを落ち着かせたり、実際に仕事を休ませてもらったりしていました。

朝の目覚めが悪く、体が重いと感じたときは休みを取っていました。 出社後も、ほかにやりたいことがあって仕事へのモチベーションが上がらないときはトイレでスマホをいじって別のことをしていましたね。

寝起きの調子が悪いと「なんか今日はだめだ」と決めつけてしまってさぼりたくなります。実際は出勤すれば問題ないことが多いですが、体調不良で一度休んだことがあります。

チームで仕事をする際、仕事に対し必要以上に人員が割かれているときは「私がこの場にいなくても仕事が回るのではないか」と思い、サボりたくなってしまいます。

気分が乗らないときや、体の疲れがなかなか取れないときは「サボりたい」とよく思っていました。 そんなときは外の空気を吸いに行ったり、少し仕事から離れる時間を作ったりしましたね。
「仕事をサボりたい」と思ってしまう理由4選
- 仕事にやりがいを感じられない
- 同僚・上司との人間関係が良くない
- 仕事が忙しくて休む時間がない
- 会社の待遇に満足していない
「仕事をサボりたい」と思いがちな人は、職場の人間関係や待遇面などで悩みを抱えている可能性があります。上記の特徴に当てはまる場合は原因を探り、周りへの相談や働き方の改善などで根本的な問題を解決しましょう。
実際に仕事をサボったことのある先輩たちのアドバイスも参考にしてみてくださいね。
仕事をサボりたいと思った理由は?

仕事をサボりたくなったときの理由を教えてください!

新しくオートバイの免許を取得して「早く乗りたい」という気持ちが先行するあまり会社を休み、免許発行センターに行ったことがあります。

新卒のときに上司からの圧力や暴言などで気持ちが落ちてしまい、仕事を休む連絡をしたうえで気分転換に出かけたことがあります。

仕事のミスで上司に叱責される日や残業が続いた翌週の月曜日に、出社する気持ちが切れて休むことがありました。
①仕事にやりがいを感じられない
「何のために働いているんだろう」「誰の役にも立っていない」と、仕事にやりがいを感じられない人は「サボりたい」と思いがちです。
第一志望の企業に就職できなかったり、やりたい仕事を任せてもらえなかったりすると、不満が溜まりモチベーションが落ちてしまいます。単純作業が多い、仕事が簡単すぎて達成感を味わえないなども、仕事にやりがいを感じられない理由の一つです。
仕事の意義を見出せずに悩んでいる人は、身近な目標を立てる、自分の強みと業務を結びつけるなどの方法でやりがいを見つけましょう。「スキルを活かせた」「成長できた」と思える瞬間が増えると、少しずつモチベーションが上がり、成果も出やすくなります。
仕事に対するやりがいが見つけられない人は以下の記事も参考にしてみてください。
②同僚・上司との人間関係が良くない
会社の同僚・上司との人間関係がうまくいかず、ストレスが溜まっている人も「仕事をサボりたい」と思う傾向にあります。
厚生労働省が2023年に実施した「令和5年労働安全衛生調査」によると、労働者の約8割が、仕事において強い不安やストレスを感じていると回答し、そのうちの約3割が対人関係で強いストレスを抱えていることが明らかになりました。
職場における人間関係の問題は、パワハラ・いじめなどに発展する可能性もあるため、事態が悪化する前に早急な対応が必要です。苦手な人が職場にいる場合は、仕事に支障がない範囲で一定の距離を保ち、可能であれば部署異動を申し出ましょう。
それでも問題が解消されないときは、心身の不調が出る前に、休職や転職も視野に入れてみてください。
次の記事では、「上司と合わない」「職場で嫌われているかも」と悩む人向けに、原因や対処法を解説しています。職場の人間関係を改善し、仕事をサボりたい気持ちを少しでも解消したい人は、ぜひチェックしてみてください。
上司と合わず悩んでいる人向け
上司と合わないときはどう対処する? 経験者に聞く原因別の改善方法
職場で「嫌われているのではないか」と悩んでいる人向け
職場で「嫌われている」と感じた9つの瞬間|辛いときの対処法とは
③仕事が忙しくて休む時間がない
仕事が多忙で休む時間がないために「仕事をサボりたい」と考える人もいます。
残業や休日出勤が続くと、疲労が蓄積して「サボりたい」と感じるのは自然なことです。しかし、長時間労働によってプライベートの時間が奪われると、ストレスが解消されず仕事が億劫になり、業務の質も次第に落ちていきます。
自分で処理しきれないほどの仕事を抱えて忙しいときは、上司に相談したり可能な範囲で周りに頼んだりして業務量を調整しましょう。仕事を処理するスキルが追いつかない場合は、タスクの優先順位をつける、締め切りから逆算してスケジュールを立てるなどの方法がおすすめです。
「なぜ忙しいのかわからない」「仕事が忙しくて辞めたい」と考えている人は、次の記事もチェックしてみてください。
④会社の待遇に満足していない
給与が仕事に見合っていない、頑張っても正当な評価を受けられないなど、会社の待遇に満足していない人も「サボりたい」と思いがちです。
どれだけ努力しても給与が低く労働環境が悪いと「頑張る意味は何だろう」と虚無感につながり、仕事に対する意欲も下がってしまいます。
会社の待遇を自力で変えるのは難しいため、収入アップや業務負担の軽減を目指して働き方を改善し、少しでも仕事のストレスをなくすことが大切です。
休みすぎに注意! 仕事をサボる人の末路とは
- 責任のある仕事を与えてもらえなくなる
- 業務に必要なスキルの習得が遅れる
- キャリアアップが難しくなる
- 人間関係が悪化して会社に行きづらくなる
仕事に対する悩みから、「サボりたい」と思うのは誰にでもあることです。しかし何度も仕事をサボる癖がつくと、周りからの信用を失い、ますます働きにくくなってしまいます。
そこで、仕事をサボる人の末路がどうなるのかをチェックし、自分の評価や周りの業務に支障が出ない息抜きの仕方を探りましょう。
仕事をサボる人は実際に職場でどのような印象を持たれるのか、先輩たちの体験談も参考にしてみてください。
実際にサボっていた人の周りからの見られ方はどうだった?

職場で実際に仕事をサボっていた人は、周りの人からどのような印象を持たれていましたか?

その人の周りの人はいつも通りかかわっていましたが、上司は呆れて会話すらしていない状況でした。 私自身はその人に対して「もう少ししっかりと仕事をしてほしい」と思っていましたね。

「またやってるよ」という印象ではありますが、営業ノルマは達成しているため強く文句は言えない状態でした。 実際に成果は認められてマネージャーに昇進しているので、成果を出していればひどい扱いを受けることはないのかもしれません。

はじめのうちはコミュニケーションを取ってもらえていましたが、自分の仕事も終わっていないのにサボってばかりいたので、だんだん周りに嫌われて異動していきました。
以下では、仕事をしない人の末路を紹介しています。社会人の本音も紹介しているので、気になる人はチェックしてみてください。
責任のある仕事を与えてもらえなくなる
「サボりたい」という理由で会社を休みすぎると、周りの信頼度が低くなり責任のある仕事を与えてもらえなくなる可能性があります。
正当な理由を伝えたとしても、会社を休む頻度が高ければ「締め切りに遅れるのでは」「スキルが身に付いていない」と懸念されるためです。
仕事を休むことでプロジェクトに遅れが生じ、取引先や顧客に迷惑をかけると、会社にとって要注意人物だと認識される可能性もあります。会社の不利益につながるリスクから、売上に直結する重要な任務につかせてもらえなくなるかもしれません。
その結果、やりがいを感じられず仕事のパフォーマンスが低下し、思い通りの成果を出せない悪循環に陥ってしまいます。
責任のある仕事を任せてもらえなくなると、単純作業が続き「仕事に飽きた」と感じることもあるかもしれません。以下の記事では、仕事に飽きてしまう状況を変える方法を解説しています。
業務に必要なスキルの習得が遅れる
サボったことが原因で責任のある仕事を与えてもらえなくなると、知識やスキルの習得が遅れる可能性もあります。
業務に必要なスキルを身に付けるためには、幅広い仕事に挑戦して経験を積まなければなりません。しかし、何度もサボることで上司に不信感を与えると「能力が低い」と判断され、簡単な仕事しか任せてもらえなくなってしまいます。
知識やスキルが身に付かないままだと、会社の居心地が悪くなるだけでなく、業績が悪化したときにリストラの対象にもなりかねません。
再び仕事をもらうためにはサボる原因を解消し、資格取得や実績を上げるなどの方法で意欲的な姿勢をアピールすることが大切です。
キャリアアップが難しくなる
仕事をサボる回数が多くなると、周りからの信用を失うためキャリアアップも難しくなります。
企業によって判断基準は異なりますが、多くの場合は勤続年数に加え、人事評価や目標の達成度、試験などをもとに誰を昇進させるか決める傾向にあります。
仕事をサボる人は、周りに迷惑をかける存在だと認識されやすいため、本人が希望しても昇進や年収アップを実現するのは厳しくなります。特に実力主義を導入している企業で働く人は、能力の高い後輩や部下に追い抜かれるかもしれません。
周りが昇進・昇給する中で自分だけキャリアアップできなければ、劣等感をおぼえる原因にもなり、ますますサボりたい気持ちが強くなってしまいます。
人間関係が悪化して会社に行きづらくなる
仕事をサボりがちになると、同僚や上司との人間関係が悪化して会社に行きづらくなります。会社をサボることでほかの社員に仕事のしわ寄せがいき、負担が大きくなり反感を買いやすくなるためです。人間関係が悪化すると、仕事で困ったことがあっても周りに助けてもらえず、居心地の悪さから再びサボる悪循環に陥ってしまいます。
ストレスなく働き続けるためには、心身の不調が出る前に無理せず休むことも大切です。ただし、その際は人間関係を悪化させないように周りへの影響を考え、できる限り迷惑にならないタイミングで休むことを意識しましょう。
職場で上手にサボる4つのコツ
- こまめにトイレ休憩をはさむ
- 音楽を聴いて気分転換する
- 集中力がいらない簡単な業務を引き受ける
- 仕事が問題なく進んでいることをアピールする
仕事を休むことで周りに迷惑をかけず、自分の評価も下げないためには職場で上手にサボる方法を実践しましょう。
集中力が途切れる前に休憩をはさんだり、簡単な業務を引き受けたりすれば適度な気分転換になりモチベーションを維持できます。職場で上手にサボっていた社会人のアドバイスも参考に、無理なくできる方法から試してみてください。
仕事をしながらどうやって息抜きしてた?

仕事中に必要なコミュニケーションを取りながら日常会話を挟んだり、水分補給をするときコーヒーを飲んだりして気持ちをリフレッシュさせていました。
「仕事をするときは集中する」「休むときはしっかり休む」などのオンオフも切り替えるよう意識しました。また、自分に余裕があるときは周りの仕事を手伝うこともしていました。
上司に媚を売ると仕事をサボりやすくなるかもしれませんが、周りの仲間には悪いイメージを持たれることが多いので、控えたほうが良いと思います。

仕事の依頼をしに行ったとき、軽い世間話や業務に関するお互いの愚痴などを話すことで煮詰まった頭を冷ましていました。話し相手が少ないときは、メールやチャットを返信するついでにプライベートのLINEを返していました。
ほかには、集中力が切れたときウォーターサーバーに水を汲みに行く、デスクから離れてフリースペースで仕事をする、外の空気を吸いに行くなどもしていました。
あまり長時間リラックスしていると「仕事をサボっている」と思われるため、席を外す際はあえて上司に声をかけ、短時間で戻ってこれるようにしていました。
①こまめにトイレ休憩をはさむ
こまめにトイレ休憩をはさむ方法は、職場で手軽に実践できる上手なサボり方の一つです。
集中力が続かないときや、苦手な同僚・上司が同じ空間にいて苦痛なときにトイレ休憩をはさむと気分転換になり、大きなストレスを抱えずに済みます。特にデスクワークをしている人は、座りっぱなしの時間が多く疲れを感じやすいため、体を動かすきっかけにもなります。
ただし、1時間に3〜4回以上のペースでトイレに行ったり、長時間こもったりすると周りに「サボっている」と判断されるかもしれません。会社側からの注意・指導が入ると評価が落ちる可能性もあるため、1日に数回、リフレッシュ程度に行くことを意識しましょう。
②音楽を聴いて気分転換する
勤務先の就業規則で禁止されていなければ、単純作業が求められるときなどに、音楽を聴いて気分転換するのもおすすめです。
休憩中に好きな音楽を聴いて気分を上げる、穏やかな曲を聴いてリラックスするなど状況に応じて使い分ければ集中力も高められます。以下の音楽には歌詞がないため、集中力が高まりやすく作業スピードも上がるでしょう。
集中力が高まりやすい音楽の例
- クラシック
- ジャズ
- ヒーリングミュージック
- 環境音楽
音楽を聴いて気分転換し、集中力を高めて効率良く働けると、仕事のパフォーマンスが向上して業務時間の短縮・やる気アップにもつながります。
気持ちが前向きになる曲を探し、仕事に支障が出ない範囲で聴いてみてください。
③集中力がいらない簡単な業務を引き受ける
仕事が忙しく、疲れが溜まって「サボりたい」と感じる人は、集中力がいらない簡単な業務を引き受けましょう。単純な仕事量は変わらなくても、簡単な業務は頭を使う場面が少ないため、精神的・時間的な余裕を持って取り組めます。
具体的にはデータ入力や資料のコピー、書類の郵送作業など「誰でもできる」「急ぎではない」業務を引き受けるのがおすすめです。集中力やモチベーションに合わせて取り組む業務を変えると、気持ちを上手に切り替えられるため、全体の作業効率も上がります。
簡単な業務で適度に息抜きし、資料作成やデータ分析など頭を働かせる仕事に注力することで、成果が出やすくなり高い評価につながるはずです。

集中力がいらない簡単な業務には、どのようなものがあるのかを教えてください!

領収書の社印を押すなど、ひたすら印鑑を押していく作業を引き受けました。 息抜きとまではいかないかもしれませんが、タイムリミットが特にない単純作業なので気分は楽でした。

会社で出している冊子などの裏面に社印を押す作業をしていました。いつもと違う仕事をやることで、リフレッシュになりました。

イベントの参加者名簿を作成したり、メッセージをコピペして各所に送ったりする作業はそこまで頭を使いませんでした。ただ、気を抜きすぎるとミスにつながるので息抜きというよりは、次の業務に向けた準備運動のような感覚でした。
④仕事が問題なく進んでいることをアピールする
周りに迷惑をかけず、自分の評価を落とさず上手にサボるためには、担当している仕事が進んでいることをアピールしましょう。トイレ休憩をはさんだり音楽を聴いたりしても、仕事をきちんとこなし成果を出していれば「サボっている」と判断されるリスクが低くなるためです。
たとえば、仕事の納期が迫っているときは上司に進捗をこまめに報告し、問題なく進んでいることを説明できると、サボっても指摘されにくくなります。目標達成に向けて努力している姿勢も伝わり、周りからの評価が上がって重要な仕事を与えられるかもしれません。
仕事への真摯な取り組みをアピールすれば、上司や同僚の信頼を得て、適度に息抜きをしても人間関係が悪化することはありません。むしろ、メリハリのある働き方は生産性の向上につながり、よりやりがいを感じられるでしょう。
職場で仕事をサボるときはオンオフの切り替えをはっきりさせ、成果を残して息抜きしやすい環境をつくりましょう。

仕事が進んでいることをアピールするために、どんなことをしていましたか?

上司への報告をこまめにおこなうことで「しっかり仕事をしている」と思ってもらえたので、上司からあれこれ言われずサボることができました。

日頃から進捗報告をおこない、上司の手が回っていない事務作業を巻き取ることで「先回りして動いてくれている」と上司からの信頼が厚くなります。

適宜中間報告をしたり、次の動き方について自分の意見も交えながら質問したりしていました。そのおかげで「業務理解をしている」という評価を得られたのか、振られる仕事の幅は広がりました。
どうしても仕事がサボりたくなってしまう場合には、仕事が合わない可能性も考えられます。以下の記事もあわせて確認してみましょう。
たまにはアリ? 会社を休んで仕事をサボるときにやるべきこと

職場で上手に仕事をサボっても、残業が続いたり人間関係のストレスが大きかったりすると、たまには会社を休みたくなる日もありますよね。
仕事をサボる日に限らず、会社を休むときは会社のルールに従って対応しましょう。直属の上司に事前に連絡するのが基本です。大事な仕事がある日は避けること、大げさな嘘にならない理由を伝えることも意識しましょう。
やるべきことを押さえたうえで会社を休むと、仕事をサボっても後ろめたさを感じずに過ごせます。
①大事な仕事がある日は避ける
会社を休むときは、業務の締め切り直前や取引先との打ち合わせなど、大事な仕事がある日は避けましょう。
大事な仕事がある日に会社を休むと、同僚や上司のスケジュールが大幅に変更される、取引先に悪い印象を持たれるなどの可能性があるためです。自分自身の評価が落ちなくても、出勤時に周りが困っている様子を見て罪悪感をおぼえるかもしれません。
「仕事をサボりたい」と思ったら事前に業務スケジュールを確認し、自分が休んでも周りに迷惑がかかりにくい日を選びましょう。大事な仕事がある日を避けて休めば、周りの負担が大きくなることを防げるため、罪悪感を抱えず休養に専念できます。
②直属の上司に電話で連絡する
当日にサボりたい気持ちが強くなり、やむを得ず休む場合は直属の上司に連絡する必要があります。
後ろめたさから連絡をするのを億劫に感じるかもしれませんが、仕事を休むときなど緊急時は上司に直接伝えるのが社会人としてのマナーです。遅くても始業10分前までに連絡し、休む理由や期間、引き継ぎ事項を伝えましょう。
「どのように伝えたら良いのかわからない」という人は、下記の例文を参考にしてください。
仕事を休むことを上司に伝えるときの例文
おはようございます。◯◯です。
昨日の夜から頭痛と倦怠感が続いています。現時点で発熱はありませんが、数日後に△△様との打ち合わせを控えているので、本日は無理をせずお休みをいただければと思います。体調が回復次第、明日には出勤する予定です。
進行中の◯◯の件については、先ほど□□さんに引き継ぎ内容を連絡しました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
企業によっては、メールやLINEで上司に連絡することを認めている場合もあります。ただし、メッセージが流れやすく無断欠勤だと勘違いされるリスクもあるため、可能であれば電話で早めに連絡しましょう。
上司に休みの連絡をするときに意識していたことは?

休まなければいけないことがわかった時点で早急に連絡し、相手にわかりやすく話を伝えることを心掛けていました。ただ「早めに伝えよう」と思い、夜中に連絡してしまうことがあったため、深夜帯は避けて上司に連絡がつきやすい時間に報告するのが良いと思います。
仕事の引き継ぎが必要なときは、同僚に休むことを伝えたうえで上司に連絡していました。復帰をする際は、必ず謝罪とともに休ませていただいた感謝を伝えるようにしていました。

まずは体調を具体的に伝えたうえで休みを取っても良いか相談し、体調管理ができておらずに迷惑をかけてしまうことについての謝罪をしました。
急ぎで対応する必要がある仕事がある場合は、詳細を伝えて代わりに対応してもらい、そのほかの仕事の進捗についてもきちんと伝えることを意識していました。そうするとスムーズに仕事の対応をしてもらえたように思えます。熱があって検査する場合は、診断結果などもこまめに連絡しました。
回復して出勤した後は、すぐに上司のデスクに行き、休みの間対応してくれたことへの感謝と心配をかけたことのお詫びをするようにしていました。出勤時に謝罪をするよりは、感謝から入るほうが上司からの印象は良いと感じていますが、会社の風土によって異なる可能性があるので要注意です。
③大事にはなりにくい理由を伝える
会社を休む理由として「身内の不幸」や「交通事故」など、大きな嘘を伝えることは避けましょう。嘘をついたことに対する罪悪感で十分な休養を取れないだけでなく、サボった事実が会社にバレると信用を大きく失うリスクがあるためです。
仕事のストレスや身体的な疲れが溜まって休むときは、頭痛や腹痛、倦怠感など病院に行くほどではない体調不良を理由にしましょう。短期間で治る可能性が高い症状を伝えると職場に復帰しやすく、周りに怪しまれるリスクも軽減できます。
上司が信頼できる人であれば、休む理由を素直に話すことで相談に乗ってくれたり、解決に向けて動いたりしてくれるかもしれません。
会社を休む理由や伝えるときのポイントについて、実際に仕事をサボった経験がある先輩たちのアドバイスも参考にしてみてください。
仕事をサボったときに使用した休みの理由を教えて!

「仕事をサボりたい……」と思った時、どのような理由で会社を休みましたか?

「体調が悪い」と言って休みました。その頃はまだ新型コロナウイルス感染症が流行する前で、検査結果を提出するルールがなかったので問題なく休めましたが、今は会社によって検査結果を聞かれる場合があると思うので注意が必要です。

頭痛や腹痛など体調不良を訴えて休みました。新型コロナウイルス感染症が流行している期間に発熱で休むと検査が必要になるため、熱と関係ない体調不良を伝えるようにし、迷惑をかけてしまったことへの謝罪や、急ぎの仕事がある場合に連携を取ることも意識していました。

「体調が悪い」と伝えて休みました。当時は新型コロナウイルス感染症が流行っていることもあったので、会社も配慮をしてくれました。 休むときの理由は明確に話し、何かある際にはこまめに報告をするのが大切だと思います。
休んだら仕事のことは忘れて過ごそう
休みが取れたら、その日は仕事のことを忘れて過ごしましょう。趣味や家族との時間でストレスを解消できると、出勤日も気持ちを切り替えて仕事に取り組めます。
会社を休むときの注意点は、外出やSNS投稿を控えることです。外出先で上司に会う、SNS投稿を同僚が見るなどでサボったことがバレると、周りの評価が落ちて職場に居づらくなるため気をつけましょう。
「サボりたい気持ちが続いている」「ストレスが解消されない」などの場合は、今の悩みを紙に書き出して思考を整理する方法がおすすめです。
仕事に行きたくない原因を分析することで解決の糸口が見え、働き方の改善に向けて動き出せます。

仕事をサボって休んだときの過ごし方を教えてください! また、会社にバレないためにはどうしたら良いですか?

大型自動二輪の免許を発行し、ツーリングをしていました。会社や自宅の周りにおらず、できるだけ遠くに出かけました。

家でゴロゴロしながらゲームしたり、一人でカラオケに行ったりしてストレス発散をしていました。自宅付近にいるのでバレることはないですが、翌日に出社した際に心配してくれた人から病状を聞かれることが多いので、矛盾がないように聞かれてもすぐに答えられるようにはしていました。

自宅でゆっくりすることが主でした。外に出たいときもあったため、その際は会社から離れている場所への外出や自宅付近での散歩など、休んだことがバレにくい行動を取っていましたね。
仕事をうまく休む方法や理由の伝え方については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみましょう。
仕事をサボったことが会社にバレたら……? 信頼を取り戻す方法とは
- 言い訳せず素直に謝る
- 原因を分析して改善策を提案する
仕事をサボりたくても、「会社にバレたらどうしよう」「誰にも信用してもらえなくなるのでは」と不安に感じる人は多いはずです。
仕事をサボったことが会社にバレたときは、言い訳せず素直に謝り、改善策を提案して行動を変える意思を示しましょう。自分自身の問題と真剣に向き合い、行動を改善する姿勢が伝わると短期間で信頼を取り戻せる可能性があります。
サボったことが会社にバレてもすぐに対処できるよう、先輩たちの体験談も合わせてチェックしてみてください。
仕事をサボったことがバレたときに状況を挽回した方法を教えて!

仕事をサボったことが会社にバレた時、どうやって状況を挽回しましたか?

とにかく結果と行動で見せて挽回するしかないと思います。 タバコ休憩のサボりがバレた友人は、より一層見られ方を意識したのはもちろんですが、新規開拓数で部署内トップの結果を残し、信頼を取り戻していました。

今までの仕事を2倍量おこなうことで信頼度を取り戻しました。 「仕事をさせてほしい」と積極的に伝える、仕事での確認作業を徹底し、さらに先輩にダブルチェックをお願いする、自分の考えを伝えながら業務を進めるなどを心掛けました。
言い訳せず素直に謝る
仕事をサボったことが会社にバレたら、言い訳せず素直に謝ると、自分自身の評価や周りとの関係性を悪化させずに済みます。
たしかに「仕事をサボりたい」と思う原因は、職場の人間関係や待遇の悪さにあるのかもしれません。しかし、会社や同僚・上司に責任を押し付けると余計に周りからの信用を失い、職場に居づらくなってしまいます。
「与えられた仕事はこなしている」「ストレス解消のために必要だった」など、相手の感情を逆撫でする言葉は避け、誠意を持って謝りましょう。
仕事のストレスで心身の不調が出ている場合は、謝罪後に改めて上司に相談すると話を聞いてもらいやすくなります。
原因を分析して改善策を提案する
信頼回復のためには、サボった原因を分析して改善策を提案することも必要です。サボったことがバレたときに謝っても、反省の様子が見られず何度も同じ行為を繰り返すのでは意味がありません。
謝罪したあとは「なぜサボったのか」「どうすればサボらずに済むのか」を分析し、改善策を立てて行動に移しましょう。たとえば、仕事の目標がないためにサボる場合は「3ヵ月以内に新規顧客を獲得する」「残業時間を10%削減する」など、具体的なゴールを設定します。
仕事量の多さで意欲が低下している人には、タスクの優先順位を整理する、業務スケジュールを見直すなどの方法がおすすめです。改善策が明確になったら、上司に報告して問題を解決する姿勢を示すと、周りの不信感が徐々になくなり信頼回復につながります。
残業時間を減らす方法を知りたい人は以下の記事も参考にしてみましょう。
仕事をサボりたい気持ちを解消する3つのポイント
- 休む日を事前に決めて有給休暇をとる
- 定期的にストレスチェックする
- 信頼できる上司や身近な人に相談する
ストレスなく働き続けるには、仕事に支障が出ない範囲で息抜きをすることが大切です。そのほか、計画的に会社を休んだりストレスチェックをしたりして、仕事をサボりたい気持ちを解消させることも意識しましょう。
過度なストレスを溜めない状態を維持できれば、突発的にサボる状況を防ぎ自分自身の評価も下げずに済みます。サボりたい気持ちが強い人は、信頼できる上司や身近な人に相談することも検討してみてください。
①休む日を事前に決めて有給休暇をとる
いきなり会社を休むとほかの社員に仕事のしわ寄せがいき、人間関係の悪化や評価ダウンにつながる可能性があります。そのため「仕事をサボりたい」と思ったときは、事前に休む日を決めて有給休暇をとりましょう。
有給休暇は「私用のため」「自己都合のため」のように、休む理由を具体的に記載する必要がないため、後ろめたさを感じにくい点がメリットです。
休むことを同僚や上司に伝え、仕事の引き継ぎもしておけば周りの負担も大きくならずに済みます。ただし短期間に何度も有給休暇を取得したり、大事な仕事がある日に休んだりすると、印象が悪くなるため注意しましょう。
②定期的にストレスチェックする
仕事をサボりたい気持ちを解消するには、定期的なストレスチェックで心身の疲れが溜まっていないか確かめる方法もおすすめです。
たとえば、厚生労働省が公開している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」では、全57問の質問に回答することで現在のストレスレベルを測定できます。
測定結果やアドバイスをもとに働き方を改善し、根本的な問題の解決や心身の回復に専念しましょう。自分のストレス状態を客観的に把握し、セルフケアをおこなうことで、過度なストレスを抱え込まずに無理なく働き続けられます。

「これはストレスが溜まっているかも……」と自分で判断するときのポイントを教えてください!

家庭でも仕事のことを思い出してしまうときは「ストレスが溜まっている」と判断します。そのため、できる限り会社を出たら社用携帯は見ないように心掛けていますね。

家に帰って家事をする気力が湧かずにそのままベッドに転がってしまったり、些細なことでイライラすることが増えたりするとストレスが溜まっていると感じます。 その場合は、休日に十分な睡眠時間を取り、プライベートでスポーツをしたり、友人と遊んだりすることで発散するようにしています。

会社から自宅に帰る際の時間で仕事の反省をしたり、寝るときに仕事の失敗などを思い出したりしてしまうときなどにストレスが溜まっていると感じます。 そんなときは、音楽を聴いたり、自分の趣味に時間を費やしたり、散歩などをしたりしています。
③信頼できる上司や身近な人に相談する
仕事をサボりたい気持ちが強いものの、その原因がわからず悩んでいる人は、信頼できる上司や身近な人に相談しましょう。上司は仕事の状況を把握しているため話を理解してもらいやすく、一人で対処できない問題でも解決に向けて動いてくれる可能性があります。
職場の人に話しづらい悩みであれば、家族や友人など身近な人に相談するとモヤモヤした気持ちを解消できるかもしれません。誰かに打ち明けることで「仕事をサボりたい」と思う原因が明確になり、解決のヒントを得られる場合もあります。
上司や身近な人への相談も難しい人は、厚生労働省が公開している「こころの耳」など、各種相談窓口を利用するのも一つの手です。第三者の視点から、客観的なアドバイスや幅広い解決策を提案してもらうことで不安な気持ちが強い人でも冷静に対処法を考えられます。
上司に相談してサボりたい気持ちを解消した先輩の体験談を紹介!

私の場合、モチベーションの落ち込みが激しかったため、上司がこまめに相談に乗ってくださり、その際にメンタルクリニックの通院をすすめていただきました。
その結果、うつ状態であることがわかったのでしばらく休職して気持ちをリセットし、復職後も同じ上司の元でストレスなく働くことができています。
直接話す時間が取れないかを相談したときに、すぐに対応してくれる人であれば信頼できる人だと思うため、本音で話しても良いのではないでしょうか。
仕事がつらい場合は転職も選択肢の一つにしよう
適度に有給休暇をとって休んだり、誰かに相談したりしても「仕事がつらい」「会社に行きたくない」と感じる人は転職を視野に入れましょう。
自分の理想と労働条件・職場の雰囲気がマッチする企業に転職することで、サボりたい気持ちが解消され、いきいきと働けます。「仕事をサボりたい」「周りに迷惑をかけたかも」という精神的な負担もなくなり、充実感を持って仕事に取り組めるはずです。

転職の一番の要因は体調不良ですが、今後続けることができないことをあらかじめ上司に相談していました。
当時の仕事は、チームで進める仕事で私が転職活動後にも続く予定の仕事でした。そのときは転職活動中だったため、改めて新しいことを学ぶ必要はないと考え、優先度の高い転職活動に集中していました。そのため、次の仕事の説明を受けてもエントリーシート(ES)や面接のことであまり集中して聞いていなかったと思います。
あらかじめ上司に相談しておくとスムーズに転職活動を進められる
転職活動と前職の仕事を両立させるため、前職での仕事が負担にならないように上司に相談し、体調と転職活動を考慮しながら調整していました。
たとえば、退職まではチームの作業記録書を確認する仕事を振ってもらったり、引き継ぎ業務に専念したりするなどです。また、仕事の時間に面接がある場合は早退し、転職活動に集中する時間を確保していました。
次の記事では、「仕事を辞めたい・疲れた」と悩んでいる人向けに、気持ちの切り替え方や転職の進め方を解説しています。仕事を辞めるか明確に判断し、次のステップに向けて行動したい人は、ぜひ参考にしてください。
働き方を改善して「サボりたい」気持ちを解消した先輩の経験談
仕事をサボりたい気持ちが強くなったとき、あえて転職を選ばず働き方を改善して会社に残った人もいます。
「仕事は好きだから辞めたくない」「でもサボりたくなってしまう」という人は、先輩の体験談からストレス解消のヒントを得ましょう。

特殊なケースですが「仕事をサボりたい」と思う行動がうつ状態からきていることが判明したため、2〜3ヵ月間休職し、体調が良くなってから職場に復帰したことがあります。
それまでは仕事を義務感や責任感で考えすぎており、家に帰ったあとや休日も仕事のことばかり考えていましたが、休職という形で物理的に仕事から離れることで義務感がなくなり「戻ったらどんなことをしてみよう」と前向きな気持ちに変換され、精神的にかなり楽になりました。
復職時に会社から配慮してもらえることもある!
転職に踏み切らなかった理由は、仕事の内容自体はとてもやりがいがあったためです。職場の人間関係が良くなかっただけなので、復職時に業務フローや上長が変わるなどの配慮をしていただきました。
また休職中に考えた結果、会社員自体を早く辞めることが最善策だと考えたため、今は現職を続けながら裏で個人事業主として働くための準備期間と位置付けました。
「仕事をサボりたい」と思うことは誰にでもある! ストレスを抱え込まないようにしよう
「仕事をサボりたい」と思う経験は、誰にでもあることです。なかでも職場の人間関係や待遇、労働条件に不満を抱えている人は「仕事をサボりたい」と思う傾向にあります。
ただし、何度も仕事をサボると周りからの信用を失いやすくなるため、タイミングを見極めて上手に息抜きしなければなりません。ストレスを抱え込まず働き続けるためにも、適度に息抜きしながら楽しく仕事に取り組みましょう。

20代半ばのころの同僚で、仕事をサボりがちな人がいました。今回のコラム執筆にあたり、現在の彼に、当時の心境を聞いてみると「何をしたら良いかわからない時、疲れた時、飲み過ぎた日の翌日とかって、サボりたくなるんだよね」と言っていました。
そして「でも、サボってみて気づくこともあるんだよね。焦りが出たりもするし、リフレッシュできることもある。サボってみるのも経験の一つなんじゃないかなと思うけどね!」とも言っていました。そう語る彼は、自身の迷走期を経て、映像・WEB制作会社を起業。現在は多数の従業員を抱える企業の良き社長として大活躍しています。
「何をしたら良いのかわからない」「何をやりたいかわからない」など、いろいろ迷ったり悩んだりした彼だからこそ、今仕事に没頭し、従業員の気持ちに寄り添える優しい社長になれているのでしょう。
サボる前に休日を取ってゆっくり休もう
どうしても「サボりたい」と思うのなら、サボる前に有給休暇を活用するなどして、周囲に迷惑をかけない範囲内でリフレッシュ日を設け、ゆっくり休養する時間を設けてみることをおすすめします。そして、「今どうして休みたいのか」「自分が何を思っているのか」「自分がどうしたいのか」など、自分に目を向けるひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。
「仕事がイヤだから、ツラいからサボってしまう」といった気持ちから安易に転職をするのは避けたほうが良いですが、もし辞めたい程に悩んでいるのであれば、一人で抱え込まずに周囲の人やハローワーク等の相談機関、キャリアコンサルタントへの相談をおすすめします。
就活力診断テストはもう使いましたか?
「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。
面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。
\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/
診断スタート(無料)






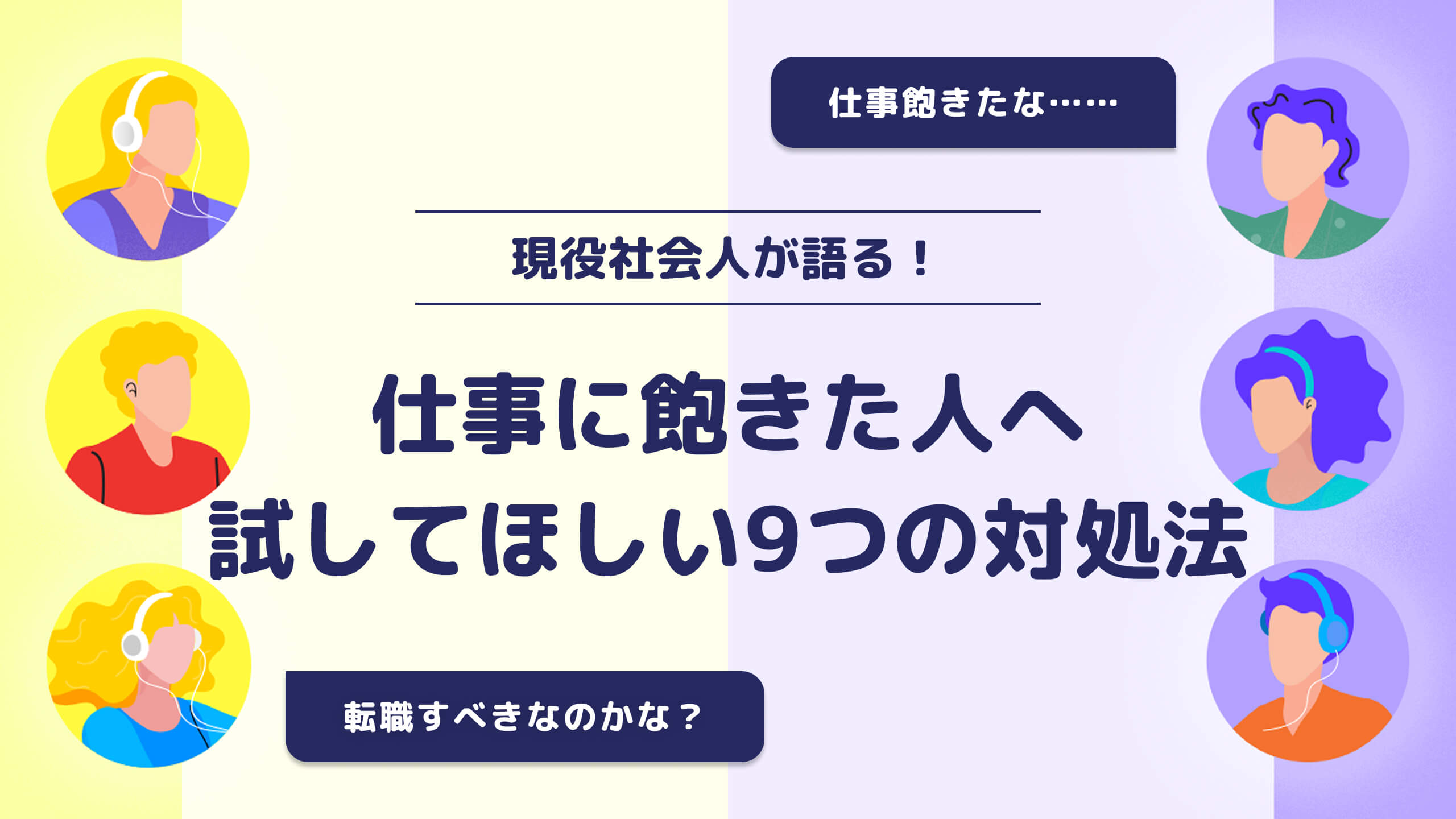



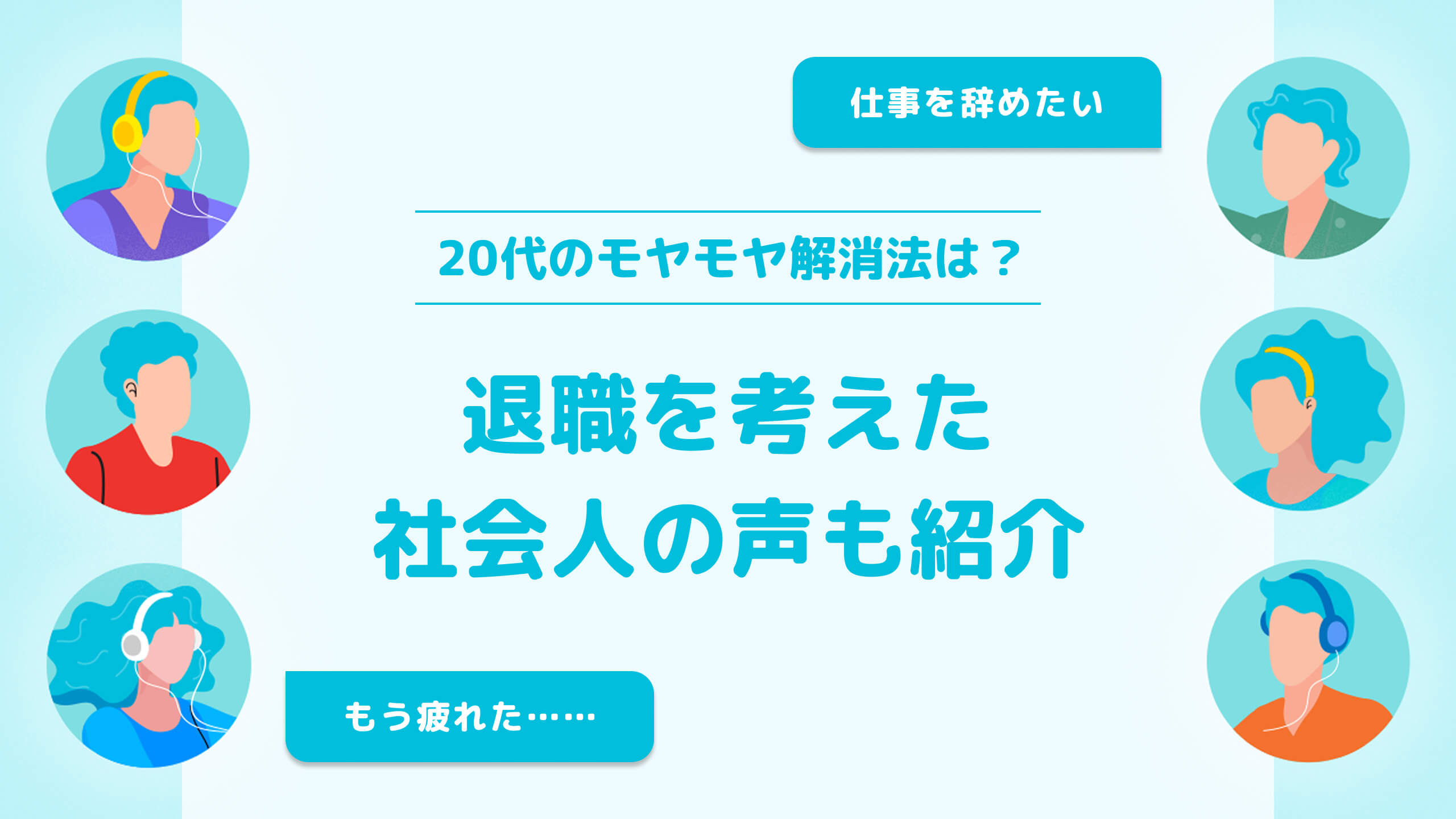






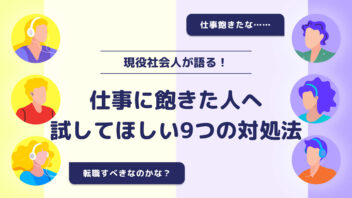

仕事に対するモチベーションが上がらないときや、体調が良くないときに「外回りに行ってきます」と言って車の中で寝ていました。