自分を責めすぎないで! 「仕事が出来ない」と感じたときは冷静に原因を探ろう
「仕事のミスが多くて周りに迷惑をかけてしまっている……」
「全然チームの役に立っていない……でもどうしたら良いんだろう」
入社してしばらく経ったはずなのに、仕事が出来るようにならないと、不安や焦りから徐々に自信を失ってしまいますよね。「仕事が出来ない」と感じたときには、冷静に原因を探って、働き方を見直したり必要なスキルを磨いたりすることが重要です。
しかし原因や改善策がわからなければ、自信のなさや周りに対する劣等感が大きくなり、仕事に行くのがつらくなってしまうかもしれません。
そこで今回は、仕事が出来ない人に共通する特徴や、つらい状況から抜け出すためのコツについて、経験者の声も交えながら解説します。
| 就活生の5大不安を解決!
オススメのツール5選 |
|
|---|---|
| ツール名 | 特徴 |
| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |
| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |
| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |
| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |
| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |
「仕事が出来ない」と感じる瞬間は? 先輩社会人にも聞いてみた
仕事上のミスは、誰にでもあることです。しかし、入社後しばらく経っても仕事が出来るようにならないと、さまざまな場面で「自分は仕事が出来ない……」と落ち込むことになってしまいます。
まずは、どのような瞬間に「仕事が出来ない」と感じるのかを振り返り、今の自分に何が足りないのかを整理してみましょう。
「仕事が出来ない」と感じる瞬間から「なぜそうなったのか」と原因を掘り下げることで、必要なスキルや解決策を見つけやすくなりますよ。
①自分のミスで周りに迷惑をかけてしまったとき
頻繁な誤字脱字や書類の不備など、自分のミスで周りに迷惑をかけてしまったときには「仕事が出来ない」と思いがちです。自分のミスのせいで周りの仕事が増えたり、上司が代わりに謝罪する様子を見たりすることで、罪悪感が募って自分を責めてしまう人も多いでしょう。
特に、言われたことを何度も繰り返してしまった場合に「自分はダメだ」と自信を失ってしまう人が多く見られます。周囲の反応が徐々に冷たくなっているのではと疑心暗鬼に陥る人も少なくありません。
「ミスは誰にでもあること」とわかっていても、周りに迷惑をかける状況が続くと消極的な気持ちになり、仕事に行くのもつらくなってしまいますよね。その気持ち自体はまったく不自然なものではなく、むしろ「自身のミスをきちんと反省できる」というプラスの性質の表れかもしれません。
仕事でミスが増えた、仕事でやらかしたと悩んでいる人は、以下の記事も読んでみてください。心が軽くなるヒントが見つかりるかもしれません。
仕事ミスばかり
「仕事でミスばかり…」現役社会人の失敗談から学ぶミスを減らす方法
仕事でやらかした
仕事でやらかした…社会人6人に聞いた失敗談&ミスを防ぐ方法
②頼まれていた仕事を期限内で終わらせられなかったとき
自分の担当業務を期限内に終わらせられないことも「仕事が出来ない」と自信を失う原因となりがちです。期限内に終わらないことでほかのスケジュールにも影響が出てしまい、思い通りに仕事を進められない歯がゆさから落ち込む人も多いでしょう。
さらに、取引先に提出する資料の作成や納品が遅れると、企業としての信用を失い、売上に悪影響を及ぼす可能性もあるため、締め切りに関して大きなプレッシャーやストレスを抱える人も珍しくありません。「早く仕事を終わらせなければ」という焦りからミスが増え、ますます自信をなくしてしまうという人もいるでしょう。
しかし、会社や上司も、若手社員への仕事の割り振り方については試行錯誤している最中です。もしかすると、期待する気持ちが先走った結果、過剰な業務をあなたに割り振ってしまっているのかもしれません。目の前の仕事が終わらないからと言って、自身の能力を過剰に卑下する必要はないかもしれませんよ。
どうしても仕事を期限内に終わらせるのが難しいと感じる人は、次の記事をチェックしてみてください。スケジュール管理や集中力を高める方法から、仕事を早く終わらせるコツをつかめます。
③顧客や取引先から厳しい指摘を受けてしまったとき
顧客からのクレームや、取引先から厳しい指摘を受け、しまいには「担当者を代えてほしい」と言われてしまったという苦い経験を持つ人もいるでしょう。そんなことがあると、申し訳ない気持ちから「仕事が出来ない」と自分を責めてしまうかもしれませんね。
自分では最善を尽くしたつもりだったのに、それが相手を不快にさせてしまった場合は特に自信をなくしがちです。厳しい指摘によって自信がなくなると、ほかの仕事に対しても消極的な気持ちになり、ミスや進捗の遅れが増えてしまいます。
特に接客業や営業職は、顧客や取引先と直接かかわる時間が長い分、指摘を受ける機会も多いでしょう。顧客トラブルに遭ってしまった場合には「自分でどうにかできたこと」と「自分ではどうにもできなかったこと」を切り分けることが重要です。
クレーム対応などが続くと仕事が辛いと感じてしまうことがあるでしょう。以下の記事では、同じような悩みを抱えた先輩たちの体験談を紹介しています。
④担当業務で思うような成果を上げられなかったとき
自信を持って取り組んだ仕事で思うような成果を上げられないと、理想と現実のギャップに落ち込んで「自分は仕事が出来ない人間なんだ」と自信を失ってしまいます。
仕事にやりがいを持っている人ほど、頑張りが成果に表れなければ仕事の意義を感じられず、モチベーションも下がってしまうでしょう。
せっかく好きな仕事をしているのに、自分を責めてやる気を失うのはもったいないことです。とはいえ、何をどのように改善したら良いのかわからなければ、自信を取り戻すのは難しいですよね。
出てしまった結果は変えられないので、まずはゆっくり一息ついてみて、落ち着いてからここからどう挽回していけばいいのかを考えていきましょう。
担当業務で思うような成果を上げられなかったと思う原因の一つとして、「要領が悪い」ことも挙げられるのではないでしょうか。次の記事では、そんな悩みの解決方法を紹介しているので、ぜひ併せて読んでみてください。
⑤周りの同期や後輩のほうが重要な仕事を任されたとき
「仕事が出来ない」と感じるきっかけとしては、周りの同期や後輩のほうが高く評価され、会社の売上に直結する重要な仕事を任されたという場面も挙げられます。
自分と一緒、もしくは自分より遅いタイミングで入社した同期・後輩が活躍する姿を見ると、強い劣等感を覚えて「自分は何をやってもダメだ」とやる気を失ってしまうかもしれません。やる気を失った状態を放置すると、集中力が続かずミスが増えて、ますます仕事に行くのがつらくなってしまいます。
周りと比べると、どうしても自分の短所にばかり目を向けてしまうものですが、そんなときこそ「今自分に出来ること」や「自分ならではの強み」を探してみてくださいね。
「仕事が出来ない……」と先輩社会人が感じた瞬間

自動車ディーラーの営業職として入社をして2年目のときです。1年目は基本的に商談や事務処理などで先輩のサポートがありましたが、2年目になりサポートがほとんどなくなりました。その途端に思うように契約がとれなくなってしまいました。
ミスを連発して上司やお客様にもお叱りを受けるようになってしまい、モチベーションが下がり「自分は仕事が出来ない人間だな」と感じてしまいましたね。

保険の営業をしていた頃、先輩のためのアポを取る際に電話対応をしていたのですが、上手く話せなかったりお客様から怒鳴られてしまったりすることが多く、「私は仕事が出来ないな」と感じていました。
保険の営業自体も大変でしたが、中でもお客様の保険加入のアフターケアが本当に大変でした。それぞれのお客様が契約した保険内容の確認だったり、足りない保険を勧めたりしなければならなかったため、かなりの苦労がありましたね。

人材派遣の客先常駐の営業をしていた際に電話口でひどく怒られたことがあり、なぜ上手くいかないのだろうと落ち込んだことがあります。
現場では派遣スタッフと同じ業務をおこなうので、コールセンターのオペレーターとして稼働していました。その際に上手くクレームに受け答え出来ずお客様を怒らせてしまい、対応に数日かかりました。
そこからしばらく自信を失って細かいミスや誤案内を繰り返してしまったこともあり、この仕事に向いていないのではないかと感じるようになりました。
自分の仕事はずばり何点? 先輩たちに悩んでいた時期と今を比較してもらった
「仕事が出来ない……」という悩みがあると、今後自分は仕事が出来るようになるのかと不安になってしまいますよね。そこで、同じ悩みを抱えていた社会人の先輩たちに、当時と今を比較してどれくらい仕事が出来るようになったのか、点数をつけてもらいました。
仕事が出来なくて大きく自信を失っている人は、解決のヒントを得るためにも、先輩たちが何を改善して点数を上げたのかチェックしてみてください。

当時が20点だとすれば、現在は80点ほどは与えていいのではないかと考えています。「仕事が出来ない」と感じたのは上手く人を頼れないときだったのですが、現在はしっかり報告や質問を出来ているからです。
私のように過度に気を遣ってしまったり、自分で何とかしたいと考えたりするタイプは、上司の様子を伺いすぎて聞けなくなってしまうことがあると思います。一見気遣いが出来る人間のように見えますが、仕事においては早く質問して解消し、次の業務に進んだ方が良いと思います。そのことを理解出来てからは、物怖じせず、気を使いすぎずしっかり質問しようと姿勢を改めることができました。
より的確に質問をできるよう、現状を整理する力や伝える力を鍛えて残りの20点を上げたいと思います。

仕事が出来なかった当時、30点くらいの点数を自分につけていました。ですが、今振り返って考えてみるともう少し点数があっても良かったのかなと思います。
なぜそのように思うのかというと、ここ近年の新入社員より当時の自分の方がガッツがあり、出世への意欲が強かったからです。なので50点くらいの点数をあげたいと思います。

新卒時代は上手くいかない時が多く、20~30点ぐらいの時期もありましたが、今はそれと比較すると80点ぐらいにはなるのかなと感じます。
上手くいかない要因として、自分の得意なフィールドではなく、苦手なフィールドで勝負してしまっていたことがあると思います。そこで、苦手なことに対して、100%の成果にこだわって正攻法で挑んで失敗するのではなく、「今自分が持っている実力の中での100%を目指す」というマインドに切り替えることを意識しました。
自分の強みを発揮できるフィールドに持っていけないかを考えることで、苦手なこともそれなりにポジティブな成果として得られていると現在は感じます。
あなたは当てはまる? 仕事が出来ない人に見られる10の特徴
- ミスの繰り返しが多い
- タスクの優先順位をつけられない
- スケジュール管理が難しい
- 仕事を進めるのが遅い
- 報告・連絡・相談がうまく出来ない
- メールの返信や電話の折り返しを先延ばしにする
- 指示を待つばかりで積極的に動けない
- 指摘されてもついつい言い訳をしてしまう
- わかったふりをして仕事内容を理解していない
- 引き受ける仕事と自分のスキルが見合っていない
「仕事が出来ない」と悩んでいるものの「何が」「どのように」出来ないのかを明確に説明するのが難しいと感じている人は多いでしょう。仕事が出来ない人に共通する特徴をチェックしてみると、自分の傾向や弱点が浮き彫りになるかもしれません。
仕事が出来ない原因を具体的に突き止められれば、それを改善するための方法も考えられるようになります。ここからは、仕事が出来ないと落ち込みがちな要因を10種類紹介します。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみてくださいね。
仕事が出来ない人の特徴は何だと思う?

仕事が出来ない人には、どのような特徴があると思いますか?

自分の経験上、相手の話を聞かない人、自分勝手な人、自分は仕事が出来ると勘違いしている人が「仕事が出来ない人」だと思います。

物事の本質を考えられない人は「仕事が出来ない人」に該当すると思います。上司からの指導に対し、どうしてそう言われたのか考える習慣がない人は、言われたそのままのことしか受け取ることができず成長につながらないため、仕事が出来ない人なのかなと考えています。

報連相が出来ない人、他責思考な人です。報連相が出来ない人は相手のニーズを把握出来ないため、常に期日ギリギリの対応になってしまうと思います。他責思考な人は自分ごとで考えられないために失敗から学べず、いつまでも同じミスをする傾向にあると考えます。
「逆に、仕事が出来る人はどのような特徴があるの?」と気になる人には、次の記事がおすすめです。仕事が出来る人の特徴から自分なりの目標を立てることで、違う視点から解決策を考えられます。
①ミスの繰り返しが多い
仕事が出来ない人には「何度指摘されても直せない」「データの打ち間違いが多い」など、ミスを繰り返す傾向があります。
社会人としての経験年数にかかわらず、仕事のミスは誰でもあるものです。しかし、ミスを何度も繰り返すと少しずつ周囲の信用度が下がり、徐々に仕事を任せてもらえなくなります。
ミスの繰り返しが多い人の例
- 上司から指示を受けた直後に作業内容を間違える
- 毎日おこなうルーティン業務で、つい必要な手順を抜かしてしまう
- 上司に確認しないまま資料を提出し、後から大幅な修正が入る
上記の状態が続いている人は、ミスを起こしやすい傾向があるかもしれません。
②タスクの優先順位をつけられない
何の業務から取り組むべきか、タスクの優先順位をつけられない人も、仕事の進捗が遅れやすく、周りから「仕事が出来ない人」という目で見られてしまうものです。
業務量は多くないのに「仕事が遅い」と言われたり、いつも締め切りに追われたりしている人は、優先順位のつけ方に問題があるのかもしれません。
タスクの優先順位がつけられない人の例
- 緊急性のあるタスクを後回しにする
- すぐに終えられるタスクに時間をかけすぎる
- 大量にタスクがあるのに、ほかの業務を引き受ける
「自分に当てはまるかもしれない」と思った人は、優先順位のつけ方を見直す必要があるでしょう。
③スケジュール管理が難しい
業務スケジュールを把握できず、物事に計画的に取り組めない点も、仕事が出来ない人の特徴です。何の仕事を、いつやるべきなのか正しく把握していないと、仕事の進め方がなりゆき任せになりがちです。
スケジュール管理が難しい人の例
- 問題なく進めているつもりでも締め切りに遅れる
- 取引先との予定をダブルブッキングする
- 会議やプレゼンの準備不足で当日の進行に支障が出る
取引先に影響が出ると、会社のイメージダウンにもつながりかねません。「自分は仕事が出来ない」と感じる人は、スケジュール管理が正しく出来ているのかもチェックしましょう。
④仕事を進めるのが遅い
タスクやスケジュール管理を徹底しても、一つの作業に時間をかけすぎると周りに「仕事が遅い」と思われてしまいます。
仕事を進めるのが遅い人の例
- 同じ業務を任された同期や後輩よりも終わるまでに時間がかかる
- 仕事を任されたとき「いつに終わらせる」のような期限を決めずに始める
- 完璧な状態に仕上げるまで作業を終えられない
仕事を進めるのが遅い人は、それぞれの作業にどれくらいの時間をかけて取り組むのか、目安を立てられていない可能性があります。
中には、自分が納得出来るレベルまで完璧な状態にしないと作業を終えられない、という人もいるかもしれませんね。自分の作業スタイルを振り返ったうえで、適切な対応をする必要があると言えるでしょう。
仕事が進まず、残業しがちという人は以下の記事も併せてチェックしてみましょう。
⑤報告・連絡・相談がうまく出来ない
同僚や上司への報告・連絡・相談を忘れがちな人は、周りとの連携がうまく取れず、迷惑をかけてしまう傾向があります。
報告・連絡・相談が出来ない人の例
- 仕事の進捗報告をつい忘れてしまい、同僚や上司の業務にも支障が出る
- チームで進めるプロジェクトの変更点について情報共有せず、後からチーム全体で大幅な軌道修正が必要になる
- 問題が発生しても周りに相談できず、一人で抱え込んで解決が遅れる
仕事に関する報告・連絡・相談を忘れると、ミスやトラブルが発生しやすくなります。特に「クレームを放置していた」といった、顧客や取引先の信頼関係を損ないかねない問題が発覚した場合には、対応も難しくなるでしょう。
こういった癖のある人の場合は、仕事に対する考え方を見直す必要があるかもしれません。
⑥メールの返信や電話の折り返しを先延ばしにする
社員や取引先からのメール・電話にすぐ対応できず、先延ばしにしがちな人も、仕事に必要な協調性や対応力が低いと見なされるおそれがあります。
連絡を先延ばしにする人の例
- 取引先からの問い合わせがあったときの対応が遅れてクレームが入る
- メールの返信や電話の折り返しよりもほかの業務ばかりを優先させる
- 「この人に連絡しても対応してくれない」と担当者や重要な仕事から外される
ほかの業務も同時に進行していると、メールの返信や電話の折り返しはつい「後でしよう」と思いがちです。しかし、相手と良好な関係を築くためには、最優先でメールや電話に対応しなければならない場面もあります。
このような先延ばし癖のある人も、自分が相手から「先延ばしにされている」と感じて落ち着かなかった経験はあるのではないでしょうか。自身の取り組みを振り返りながら、自分も相手も仕事を進めやすくなるコミュニケーションのあり方を探ってみましょう。
⑦指示を待つばかりで積極的に動けない
次に何をするべきなのか、自分で考えずに指示を待つばかりの人は「働く意欲がない」とみなされ、簡単な仕事しか任されなくなるかもしれません。
仕事で積極的に動けない人の例
- 上司に「もっと自分で考えて行動したほうがいい」と、たびたび注意される
- 困っている様子の人がいても「邪魔になるかも」と遠慮してしまう
- 任されるまで仕事を引き受けないため、周りに業務がしわ寄せされる
与えられた仕事の質は高くても、積極的に動けないと周りが毎回指示しなければならないため、余計な業務が増えて迷惑をかけてしまいます。
「仕事のやる気が出なくて積極的に動けない」という人は、次の記事をチェックしましょう。やる気が出ない原因や、自分に合ったモチベーションの上げ方を知ることで、自然と積極的に動けるようになるかもしれません。
⑧指摘されてもついつい言い訳をしてしまう
仕事が出来ない人ほど、周りにミスを指摘されても素直に認められず、つい言い訳をしてしまう傾向があります。
指摘されても言い訳をしてしまう人の例
- ミスの原因が自分だとわかっていても、つい周りのせいにして関係が悪化する
- 改善策を考えないため、同じミスを繰り返す
- 取引先から指摘されたミスも相手のせいにして、担当者を変更されたり契約を打ち切られたりする
自分が招いたトラブルにもかかわらず周りに責任転嫁をしてしまう癖があると、職場の人間関係が悪化して仕事に必要なスキルを教えてもらえず、いつまでも成長できなくなってしまいます。
指摘されても言い訳をしてしまうのは「仕事で失敗してはいけない」「ミスが怖い」という気持ちを強く持っていることが原因だと考えられます。ミスへの恐怖が大きいためについつい言い訳をしていないか、一度自分の気持ちを整理してみてください。
⑨わかったふりをして仕事内容を理解していない
先輩や上司に仕事を教えてもらうとき、わかったふりをして何も質問せず、十分に理解しないまま業務に取り組んでしまう人もいます。正解がわからないまま行動してしまったら、ミスが多くなってしまうのも無理はないでしょう。
わかったふりをしてしまう人の例
- 上司の指示とまったく異なる資料を提出する
- 個人の解釈をほかの社員や取引先に伝えて混乱させてしまう
- 何度も同じ部分で修正が入り、仕事を終わらせるのが遅くなる
仕事の全体像を把握していないために気付けなかったミスが、会社の信用問題にかかわる大きなトラブルに発展する可能性もあります。「わかったふり」をしがちな人は、仕事の取り組み方を見直す必要があるかもしれません。
⑩引き受ける仕事と自分のスキルが見合っていない
仕事が出来ないと感じる人の中には、自分のスキルと見合わない、難易度の高い業務を引き受けてしまっているケースも見られます。
仕事とスキルが見合っていない人の場面例
- 仕事の内容を何度聞いても理解出来ず、期限内に終えられない状態が続いている
- 仕事を引き受けたものの、自分では対応できず全体の進行に遅れが生じる
- 難しい仕事だとわかっていても、周りの期待に応えるため無理をしてしまう
仕事と自分のスキルが見合っていないと「同期や後輩よりも役立たずなのかも」「自分にはスキルがない」と落ち込んでしまいますよね。
ただ、このケースは自分の業務状況やスキルを上司に正しく把握してもらえていない可能性も十分に考えられます。冷静に振り返り、対処をする必要があると言えるでしょう。
スキル不足のせいとは限らない! 仕事が出来ない要因となる4つの職場環境

なかなか仕事が出来るようにならない原因は、必ずしも当人のスキル不足とは限りません。実は、職場の環境自体が問題を抱えているケースも少なくないのです。
「仕事が出来ない…」と悩んでいる人は、今の職場環境がスキルの成長を妨げていないかどうかもチェックしてみましょう。
職場の環境そのものに問題がある場合、自分の力だけで改善しようとしても、難しい部分もあるでしょう。ただ、自分の無力感の原因がスキル不足だけではないと知ることで、つらい気持ちが少し楽になるかもしれません。
①上司が多忙で仕事に必要なスキルを教えてもらえない
仕事を教えるポジションである上司自身が忙し過ぎる場合、部下側は必要なスキルを身に付けられず、成長のチャンスを得られなくなってしまいます。
仕事でわからないことがあっても、上司の忙しそうな様子を見た結果、質問するのを遠慮してしまうというケースは珍しくありません。仮に質問できても、きちんと対応してもらえず、結局疑問が解消されないまま仕事を進めてしまうという場合もあります。
その結果ミスをして「自分のせいだ」「私が仕事が出来ないんだ」と悩んでいる人も、実は少なからずいるかもしれません。
②チーム内での相談や協力がしづらい雰囲気がある
チーム内の人間関係が悪く、相談・協力するのが難しい職場で働いている人も、なかなかスキルアップが出来ないかもしれません。スキルを伸ばすうえで効果的なのは、考え方や価値観が異なるメンバーと仕事をしながら、新しい視点や知識を得ることです。
しかし、チーム内で協力する姿勢が見られず、困ったことがあっても相談するのが難しい環境だと成長のチャンスに恵まれないでしょう。
職場のコミュニケーションに難しさを感じている人は、それが「自分の努力で改善できるレベルなのかどうか」を一度振り返ってみるのも良いかもしれません。
職場環境が原因で「働きたくない」「人と関わりたくない」と悩んでしまっている人はこちらの記事も読んでみてくださいね。
③一人が担当しなければならない業務の量が多すぎる
仕事のミスや遅れが多い人は、周りに比べて自分の担当業務が多すぎないかを確認してみるのもおすすめです。業務量が多すぎると、タスクをこなすだけで精一杯になり、スキルアップに向けた勉強の時間や、じっくり仕事に取り組むための時間を確保できません。
スキルが伸びなければ仕事の質が上がらず「自分は仕事が出来ない」と自信を失う原因にもなります。「自分なりにタスク管理やスケジュール管理を頑張っても、今の業務量をこなすのは物理的に難しい」と感じる場合には、上司に相談してみる必要があるでしょう。
④パワハラによって本来の実力を出せない
パワハラが横行している職場の場合、上司の高圧的な態度によってネガティブな気持ちになり、本来の実力を出せない可能性があります。
どれだけ仕事が出来る人でも、否定的な言葉をぶつけられたり、毎日の残業を強いられたりすると「自分は仕事が出来ない」と精神的に疲れ切ってしまい、自信を大きく失うものです。
パワハラによって本来の実力を出せない場合は、働き方を改善するよりも、まずは社内の相談窓口を利用して職場の実態を伝えましょう。
先輩社会人のアドバイス付き! 仕事が出来ない状況から抜け出す10のコツ
仕事が出来ない状況から抜け出す10のコツ
- タスクの優先順位をつける
- 報告・連絡・相談を徹底する
- わからないことはすぐに解消する
- メモを取る癖をつける
- ミスから学ぶ姿勢を持つ
- 仕事が出来る人のお手本を見つける
- マニュアルやチェックリストを活用する
- スキルアップの機会を積極的に作る
- 仕事の振り返りを定期的におこなう
- 完璧主義ではなく完了主義を心掛ける
仕事が出来ないと感じる原因がわかったら、少しずつ仕事の進め方を改善していきましょう。ここで紹介する10個のコツを参考に働き方を見直しながら、スキルを磨いていくのがおすすめです。
ただし、10個のコツを一気に取り入れようとすると、どれも中途半端になって思うようにスキルが伸びない可能性があります。そのため、まずは自分に合った方法を2〜3個選んで試してみてください。
先輩社会人のアドバイスも参考にすると、いろいろな解決策が見えてきますよ。
仕事が出来ない状況から抜け出すためにやったことは?

自分の感情を判断軸から切り離し、代わりに会社視点で「どう動いたら得なのか」を考えて動くようにしました。個人的な感情が混ざると、気を遣いすぎて質問ができなかったり、苦手な上司や同僚とうまくコミュニケーションを取れなかったりすると思います。
自分の感情を切り離すことでスムーズな報告・連絡・相談が出来るようになった
私は直属の上司に、支店で最も厄介者として扱われている人がおり、その人に質問や情報の共有をしなければならないという課題がありました。感情が混ざると毎回嫌だなと思いますし、余計に質問タイミングに気を遣います。
このとき、判断軸を会社視点に移すことで、自然と「早く質問したほうがいいな」「これは共有しておくべきだな」と合理的に考えて必要な行動を取りやすくなりました。一言でいうと、「視点を変えて仕事と割り切る」という考え方です。
この考え方を自分の中に確立してからは、以前より迅速な報連相をおこなえるようになりましたし、苦手な人との仕事につらさを感じることも格段に少なくなりました。

以前自動車ディーラーの営業職だったときのことです。なかなか自分の思ったように契約を取ることが出来ずミスも連発してしまい、後輩にも成績を追い抜かれてしまいました。
当時は後輩に負けてしまったことが本当に悔しくて、「自分は仕事が出来ない」と落ち込み、なんとか仕事が出来る人間になりたいと思うようになりました。
自分なりの勉強を積み重ねることで確実にスキルアップ!
それをきっかけに勉強をするように。先輩の行動を見て自分にない良いところをマネをして勉強をしたり、読書をして新しい知識や資格や教養を身に付けたりするようにしました。
その結果、自分が変わったことを上司やお客様が気付いてくださり褒めてくれました。また、自分に自信をつけることができ、契約件数を伸ばし後輩・先輩よりも良い成績を残すことが出来たので、努力が報われて良かったです。
①タスクの優先順位をつける
効率的に仕事をするためには、まず自分が今抱えている業務を整理し、タスクの優先順位をつけてみましょう。
何の仕事を・どの順番で取り組むのかを明確にすると、今やるべきタスクを頭の中で整理でき、焦らず集中して業務に取り組めます。その結果、大量のタスクがあっても、効率よく期限内に終えられる業務を増やせるでしょう。
タスクの優先順位をつける方法
- 今抱えているタスクを洗い出す
- 今日やるべきことと、明日以降にやることを分ける
- 今日やるべきことに対して「緊急度」「重要度」の高いものから順位をつける
緊急度が高い仕事とは「締め切りが迫っているもの」のことで、重要度が高い仕事とは「売上や成果に直結するもの」のことです。
今抱えているタスクを整理するときは、思い浮かんだ仕事から紙に書き出し、そこから優先順位をつけましょう。優先順位をつけたら、それぞれのタスクにどの程度時間がかかるのか、所要時間の目安も立てておくと、一日の業務スケジュールも組みやすくなります。
優先順位のつけ方については、先輩たちのアドバイスも参考にしてみてくださいね。

どのような基準でタスクの優先順位をつけているのか教えてください!

定番ですが4つの領域に分けてタスクを考えます。 「緊急で締切があるもの」、「緊急ではないが締切があるもの」、「緊急で締切がないもの」、「緊急でもなく締切もないもの」に分けて、タスクの優先順位をつけて仕事に取り組むことを心掛けています。

小さいタスクに最初に取りかからないことです。一番元気な状態で小さいタスクの処理に体力を使ってしまうと、そのあとの大きいタスクで力尽きてしまいます。 大きいタスクをやり切ったあとの息抜きとして、最後に小さいタスクと向き合うというような優先順位のつけ方をするべきかなと思います。

仕事の期限と、上長や相手のスケジュールを見て優先度を決めています。相手のスケジュールが詰まっている場合はタイミングが限られているので、そこを最優先にスケジュールを組み、その日のうちにやること、緊急度が高いもの、緊急ではないが優先度の高いものの順に進めていきます。
②報告・連絡・相談を徹底する
同僚や上司への報告・連絡・相談を丁寧かつ迅速におこなうことも、仕事が出来ない状況から抜け出すためには重要です。
疑問点や業務の進捗など、些細なことでも情報共有を徹底することで、同僚や上司は「その対応で良いのか」「次に何をするべきか」と適切な判断がしやすくなり、結果的にプロジェクトを成功までつなげやすくなります。
報告・連絡・相談をするとき、どのように伝えたら良いのか悩む人は、以下の例文を参考にしてください。
同僚や上司に報告するときの例文
◯◯の資料作成が完了しました。お手数ですが、ご確認いただけますでしょうか?
報告する際には、何の業務が終わったのか、結論から話し始めるとスムーズに内容を理解してもらえます。
同僚や上司に連絡するときの例文
◯◯社との打ち合わせですが、開始時間が10時から11時に変更になりました。△△さんと□□さんにも伝達済みです。
連絡事項について報告するときには、誰に伝達済みなのかも併せて連絡すると、上司もチーム全体の状況が把握しやすいでしょう。
同僚や上司に相談するときのOK例文
◯◯の件について、A案とB案のどちらで進めるべきか迷っています。今のところA案の△△というメリットが大きいと感じ、私としてはA案の方を推進していきたいのですが、B案の□□な点も見逃せず、判断が難しいです。どのように対応すると良いのか、アドバイスをいただけますでしょうか。
同僚や上司に相談するときのNG例文
◯◯の件について、A案とB案のどちらで進めるべきか迷っています。どちらにすると良いでしょうか。
相談するときには、その時点における自分なりの考えを入れるのがポイントです。NG例のような表現では、判断を丸投げするような印象を上司に与えてしまいます。自分なりの方向性を固めたうえで相談することを心掛けましょう。
③わからないことはすぐに解消する
業務上の不明点を曖昧にしたまま作業を進めると、思わぬミスを起こしてしまうことがあります。時には大きなトラブルに発展するケースもあるため、仕事でわからないことはすぐに質問し、解消することを心掛けましょう。
「質問をすることで、仕事が出来ない人だと思われるのでは」と心配になる人もいるかもしれません。たしかに、何度も同じ質問を繰り返すと「仕事が出来ない」と思われてしまう可能性があります。そこで、質問の仕方にはある程度の工夫が必要です。
とにかく、最悪なのは「わからないのに質問をしないこと」だと踏まえ、ミスを減らせるよう些細な疑問でも質問し、内容を十分に理解したうえで仕事に取り組むことが重要です。
質問相手やタイミングを探るときの例
- 自分の担当業務を過去に誰が担当していたのか同僚に聞いてみる
- 社内ツールで上司の業務スケジュールをチェックする
- ほかの人が上司によく話し掛けるタイミングを見ておく
上記の方法で、適切な質問相手やタイミングを事前に把握しておくと、困ったときも迷わず質問出来ます。
④メモを取る癖をつける
仕事を効率的に覚えてミスを減らすためには、上司に教わったことや作業中に間違えやすいポイントについて、メモを取る癖もつけましょう。ただし、やみくもにメモを取っても何をどこに書いたのかがわからなくなり、かえって効率が悪くなるため注意が必要です。
仕事のメモを取るときのポイント
- タイトル、日付、場所を最初に記入する
- 要点を箇条書きでまとめる
- 後から追記出来るように余白を空ける
担当業務や会議の名前など、メモの概要がひと目でわかるタイトルがあると、後から見返すときも探しやすくなります。要点の箇条書きでまとめる方法は、メモを見たとき内容を簡単に整理出来るのがメリットです。
メモを取る癖をつけるためには、常にメモ帳を携帯したりデータを見やすい場所に保存したりして、いつでも書ける状態にしておきましょう。

仕事でメモを取るときのコツを教えてください!

まず上司に仕事を教えてもらうときは、走り書きでざっとメモをします。その後、手が空いたときや帰宅後に復習を兼ねて綺麗に見やすく書き直すと理解が深まるのでおすすめです。

上司に言われたアドバイスをしっかりメモに残し、周りの人がやっている行動も観察しながらメモを取ります。そして、メモしたものをまとめたうえで、作業前に見直しをしていますね。

言われた内容をメモし、疑問点があったら質問して書き加えるようにしています。その後実際にやってみて、自分なりの言葉に落とし込むと、ミスしやすいポイントもわかって覚えるのが早くなると感じています。
⑤ミスから学ぶ姿勢を持つ
ミスの原因を分析し、そこから学んだことを次に活かす姿勢も重要です。
なぜ失敗したのかを明確にし、同じミスを繰り返さないように仕事への取り組み方を改善することで、徐々に必要なスキルが身に付き自信にもつながります。
ミスや失敗をしてしまうことは必ずしも悪いことではありません。自分が成長出来るチャンスと捉えて前向きに受け止めましょう。
仕事でミスをしたときの対処法
- 同僚や上司、取引先から受けた評価を素直に受け止める
- 業務のプロセスを振り返ってミスの原因を探る
- 改善策を考えて次の取り組みに活かす
ミスの原因を探るときは、仕事の進め方に問題があったのか、メンバーとの連携はきちんと取れていたのかなど、さまざまな角度から振り返るのがポイントです。
改善策を考えたら、内容に問題はないか同僚・上司にチェックしてもらうと、自信を持って次の業務に活かせます。
⑥仕事が出来る人のお手本を見つける
スキルアップや業務改善の方法を見つけるのが難しい人には「仕事が出来る」と思う身近な存在をお手本にし、そこからヒントを得る方法がおすすめです。
お手本となる存在がいれば「こんな人になりたい」と目標を設定しやすくなり、高いモチベーションで仕事に取り組めます。
いつでも仕事の様子を観察出来るよう、同じエリアで働いている社員をお手本にすると良いでしょう。気軽に話せる関係性であれば、休憩時間や一緒に仕事をするときに「どのようなことを意識して仕事に取り組んでいますか?」と聞いてみるのも一つの手です。
仕事が出来る人から良い点を吸収したら、自分の業務に合わせてアレンジし、積極的に働き方を改善しましょう。

仕事のスキルを伸ばすために、どんな人をお手本にしたら良いですか?

自分とスキルがかけ離れた先輩をお手本にするより、自分より少し出来る先輩をお手本にして徐々にレベルアップをしていきました。

特定の人に絞らず、さまざまな人の長所だけを上手く盗もうと心掛けていました。なんでも出来るすごい人もいますが、そういう人さえも持っていない長所を意外な人が持っていることがよくあります。 憧れや目標を一人に定めるのも良いですが、いろいろな人を広い視点で観察する中で自分に合った理想のモデルを構築していく方法もおもしろいのでおすすめしたいです。

それぞれの人に良さがあるため、幅広く観察してメモを取り、それを自分の中に少しでも取り入れるように頑張って行動していました。 観察するときは相手の行動を見ながら「自分ならこうする」と考え、相手の良い点は積極的に取り入れるようにしていましたね。
⑦マニュアルやチェックリストを活用する
仕事をなかなか覚えられずにミスが増えがちな人は、マニュアルやチェックリストを活用して作業手順を丁寧に確認しましょう。
仕事の質を高めるには、まず「何の作業に」「どのように取り組むのか」を十分に理解しなければなりません。仕事を覚えるまで多少時間はかかりますが、一つひとつの作業を丁寧に進めていくうちに、ミスは確実に減っていきます。
マニュアルを見るときは「重要な部分に線を引く」「付箋を貼る」など、間違えやすいポイントを見落とさない工夫をしてみましょう。
チェックリストの活用は、作業手順の多い仕事に効果的です。事前に何のタスクがあるのかを確認し、一つずつチェックを入れながら作業を進めると、ミスが起こりにくくなります。
⑧スキルアップの機会を積極的に作る
仕事が出来ない原因や足りない知識が明確になったら、勉強や研修などスキルアップの機会を積極的に作り、業務に役立てましょう。
仕事に活かせるスキルアップの機会
- 書籍やオンライン講座で勉強する
- 社内外のセミナーや研修に参加する
- 仕事に必要な資格の取得を目指す
書籍やオンライン講座は、プライベートの時間や通勤中に無理なく勉強出来る方法です。すきま時間を使って知識やスキルを身に付け、仕事に活かすことで業務効率が上がり成果を出しやすくなります。セミナーや研修に参加すると、書籍やオンラインでは得られない、業界に関するリアルな情報を得られるでしょう。
仕事に必要な資格の取得を目指すと明確な目標ができるため、スキルアップに向けて高いモチベーションで勉強に励めます。

職場やプライベートでどのようにスキルアップの機会を作っていましたか?

上司の動きをよく見て「こう動いたら良いかもしれない」という分析とシミュレーションを業務外でおこなっていました。すると、先回りで業務をおこなえるようになり、それが信頼につながって新たな仕事を振ってもらえるという、スキルアップの好循環につながっていったように思えます。

プライベートの時間に本を読むようにしました。 特に自己啓発本を読むことにより、自分自身の考え方や新たな知識を得ることが出来てスキルアップにつながりました。

人前に立って話すことが苦手だったので、副業でスポーツ大会の運営スタッフとして稼働し、人前に立って簡潔に話すスキルを習得しました。 私は理論よりも場数を踏んで覚えるタイプのため、経験値を積んで本業に活かしました。
⑨仕事の振り返りを定期的におこなう
仕事で学んだこと・ミスしたことを定期的に振り返り、改善点を見つけて次に活かすこともスキルアップのためには必要です。
忙しくて時間を確保するのが難しい人は、仕事が終わる直前の5〜10分だけでも問題ありません。どれだけ時間が短くても、効率的にスキルを伸ばすには毎日振り返りをおこなうのがポイントです。
仕事の振り返りをおこなうときは、単純にその日の出来事を言葉にするだけでなく、一日の成果やミスについて自分自身に質問を投げかけてみましょう。
仕事の振り返りで自分に質問すること
- 今日うまくいったことは何ですか?
- 今日うまくいかなかったことは何ですか?
- 今日と同じ仕事をもう一度出来るとしたら、どんなことに気をつけますか?
学んだことを翌日の業務に活かし、それをまた振り返ることで徐々に仕事の質が高まり、会社に貢献する「仕事が出来る人」になれますよ。
⑩完璧主義ではなく完了主義を心掛ける

常に100%を目指す完璧主義の人は、どうしても仕事が遅くなりがちです。そんな人はまず終わらせることを優先する「完了主義」という考え方を取り入れるだけでも、仕事の遅れを防げるようになります。
完了主義は、100%の結果を出すことより、70〜80%の完成度でも期限内に終わらせることを重視する考え方です。早めに周りからフィードバックをもらうことで効率的に改善出来るため、長期的に見ると完了主義のほうが高い成果を出せるのです。
完璧を追い求めるあまり、仕事の進捗が遅れている人は「まず完成させる」ことを目指し、100%までたどり着けなくても一旦チェックしてもらいましょう。
質の高さだけにこだわらず、周りと協力しながら100%に近づけることを意識すれば、アドバイスをもらえる機会が増えて成長につなげられます。
「出来ない」自覚は成長のチャンス! 自分の弱みを逆転させる3つの考え方
自分の弱みを逆転させる3つの考え方
- 弱みをあえてオープンにして協力を仰ぐ
- 弱みを補うためのプロセスを仕組み化する
- 自分の困りごとをチーム全体の改善につなげる
仕事が出来なくて悩んでいる人は、考え方を変えるだけでも大きな成長を遂げられるかもしれません。「仕事が出来ない」と落ち込む気持ちは「仕事が出来るようになりたい」と思う向上心の表れでもあります。
その向上心を仕事に活かし、弱点を克服したり補ったりしながら自信を取り戻しましょう。
①弱みをあえてオープンにして協力を仰ぐ
弱みを肯定的に捉えて成長につなげるためには、自分の苦手なこと・わからないことをあえてオープンにし、周りの力を頼ってみるという手段もおすすめです。
案外、人は頼られると嬉しいものです。「自分を信頼してくれている」と感じ、良好な関係を築けることもあります。また、弱みをオープンにすることでアドバイスをもらう機会が増え、さまざまな人から新しい知識やスキルを習得出来る点も大きなメリットです。
「△△が得意な◯◯さんだからお願いしたい」という信頼の気持ちを伝えられれば、相手も前向きな気持ちで仕事を引き受けてくれますよ。

仕事で周りの協力を仰ぎやすくするために意識していたことを教えてください!

自分は仕事が出来ない方ですが、愛想良く振る舞うように心掛けていました。その結果「しょうがないから協力するか」という雰囲気に持ち込んで協力を仰ぎました。

普段から雑談などや冗談を通して、周囲との関係構築を怠らないようにしました。愛嬌があったり人柄の良さを認めてもらえたりすると、いざというときもフォローしてもらえることが多いです。 部門間で持ちつ持たれつの関係にある状況だと、お互いに支え合うことが前提になっている業務が多いので、協力を仰ぎやすいのではないかと経験を通して感じています。

いざという時に助けてもらえるよう、日頃から挨拶するなどこまめにコミュニケーションを取り、周りが困っているときは私自身も手を差し伸べることを意識しています。
②弱みを補うためのプロセスを仕組み化する
人には向き・不向きがあるため、どれだけ頑張っても弱点を克服するのが難しい場合もあります。そこで自分の得意分野や業務効率化のツールを活用すると、ミスや進捗の遅れを減らす仕組みができ、効率的に仕事が出来ます。
たとえば、メールで誤字脱字が多い人は、送信前に文章校正ツールでチェックする習慣をつけましょう。専用ツールを導入しなくても「Word」や「Googleドキュメント」などの普段使っているソフトを活用すれば気軽にチェックできますよ。
チームで仕事に取り組む際は、「苦手なデータ分析をほかの人に依頼し、自分は得意なプレゼン力を活かして発表資料を作成する」という方法によって弱みを補うという方法も考えられるかもしれません。
自分の強みを何に活かせるか、どのようなツールで弱点をカバー出来るのかを考えると、無理にスキルを伸ばさなくても解決の糸口が見えてきますよ。
③自分の困りごとをチーム全体の改善につなげる
個人的な悩みをチームの課題として共有すると、全体の仕事を見直せるだけでなく、自分自身もスキルアップのヒントとなる新たな学びを得られます。
たとえば、ある取引先の対応に困っているとき、メンバーに聞いてみたら「私も悩んでいた」ということがあるかもしれません。そこから改善策を共有することで、対応の難しい取引先とも良好な関係を築くヒントが得られるでしょう。
自分の困りごとをチーム全体の改善につなげる際は、ミーティングなど話し合いの場で「◯◯に悩んでいるのですが、どのように対応したら良いでしょうか?」と投げかけてみてください。
チームとしての改善策がまとまったら実践し、定期的に振り返りをおこなうことで、より良い案が見つかり、さまざまな知識・スキルを吸収出来ます。
無理は禁物! どうしても仕事が出来なくてつらいときの対処法4選
- 自分の強みや仕事で達成したいことを見つめ直す
- 上司に相談して仕事の内容を変えてもらう
- 休暇を取って仕事から離れる時間を作ってみる
- 異動や転職をして働く環境を変える
「仕事が出来ない……」と悩む人のなかには、あらゆる方法を試したものの、それでもスキルが伸びず、つらい気持ちを抱えている人もいるかもしれません。
「仕事が出来ないから社会人失格」ということは決してありません。先輩のアドバイスも参考にしながら、つらい気持ちを乗り越えるヒントを見つけましょう。
また、次の記事では「会社に行きたくない」と感じる原因や気持ちを切り替えるコツを解説しています。なかなか仕事が出来るようにならず、会社に行きたくない気持ちが強くなっている人は、こちらもチェックしてみてください。
仕事が出来なくてつらい時期を乗り越えた先輩社会人のアドバイス

個人的な考えになりますが、思い悩むときはどうしても視野が狭くなってしまうと思います。「仕事が出来ない」と週5日思い詰めるわけですから、委縮してしまうのも当然です。
そういうときは、少し苦しいかもしれませんが、「どうして仕事が出来ないのか」を深掘りしてみてほしいです。私のように「気を遣いすぎて必要な質問ができない」からなのかもしれませんし、ほかの理由かもしれません。
とにかく「仕事が出来ない」と大きく捉えるのではなく、悩みのタネを分解して自分でどうにかできる範囲までハードルを下げていきましょう。すると「これを学んだらいいのかも」「こういう意識が足りていないのかも」などの対処法が見えてきます。
「仕事が出来ない」という漠然とした悩みに頭を抱えるとつらくなってしまうので、自分が無理なく立ち向かえる範囲で考える工夫をしてみてください。

私も「仕事が出来ない」と悩み、つらい思いをしてきました。仕事が出来るようになりたいときは、業務内容や働き方を変える前に自分自身のモチベーションや考え方を見直し、意識を変えていくのが良いと思います。
私は自己啓発本を読み、新たな知識を得られるような経験をするように心掛けました。今悩んでいる人たちも、業務を見直す前にまずは自分自身を見直してみましょう。
①自分の強みや仕事で達成したいことを見つめ直す
どれだけ頑張っても仕事が出来るようにならない場合、今の職場が自分に合っていない可能性があります。自分の強みを今の職場で活かせているか、働くうえで何を達成したいのかを整理することで、本当にやりたいことや実力を発揮出来る仕事を見つけられるかもしれません。
自分の強みや仕事で達成したいことを見つめ直すには、徹底的な自己分析が必要となります。自己分析は就活・転職をする際におこなうイメージが強いかもしれませんが、自分の考えや価値観を見直すうえでも効果的な方法です。
今まで自分はどのようなスキルを活かして困難を乗り越えてきたのか、紙に書き出して棚卸ししましょう。その中には、今の仕事に活かせる知識やスキルがあるかもしれません。
②上司に相談して仕事の内容を変えてもらう
自己分析の結果、「担当業務が自分のスキルや適性に見合っていない」と感じたら、上司に相談して仕事内容や業務量を調整してもらうという方法も考えられます。
仕事の内容を変えてもらうべきか判断に迷っているのであれば、まずは今の気持ちを打ち明けてみるだけでも構いません。実際に担当を変えてくれる場合もあれば、それ以外の解決策を示してもらえる場合もあるでしょう。
業務量が多すぎる場合はタスクを減らしてもらったり、苦手な業務をサポートしてもらったりするだけでも気持ちの負担が軽くなり、仕事に取り組みやすくなります。
直接伝えるのが難しい場合は、メールやチャットなどを使うと、心理的なハードルを下げられますよ。
③休暇を取って仕事から離れる時間を作ってみる
仕事が出来なくてつらいときは、有給休暇を取って自分の時間を作り、リフレッシュに専念してみましょう。仕事について何も考えない時間を意図的に作ると、日頃のストレスから解放されて気持ちを切り替えられます。
常に仕事のことが頭から離れないほど悩みが深刻な場合は、休暇のときに無理にリフレッシュのための行動を取り入れなくても構いません。まずはじっくり考える時間を優先し「仕事が出来ない」と感じる原因を探ってみてください。家族や友人など、信頼出来る身近な人に相談するのも一つの手です。
目の前の業務に追われながらでは、ゆっくり考える時間も作りにくいものです。仕事から離れた状態で今の状況を客観的に見れば、落ち着いて原因や解決策を考えられるようになりますよ。
④異動や転職をして働く環境を変える
仕事が出来ない原因を探った結果、「そもそも今の仕事が自分に合っていない」と判断した場合には、自分の強みやスキルを活かせる部署や企業への異動・転職も検討しましょう。
過酷な労働環境で働いている、パワハラを受けているといった場合にも、自分の身を守るためには異動・転職を視野に入れてみてください。
異動や転職によって今よりもストレスが少ない環境で働けるようになれば、前向きな気持ちで仕事に取り組めるため、自然とモチベーションが上がってスキルも伸びるでしょう。
次の記事では「自分に向いてる仕事」の意味や、向いてる仕事を見つける方法を解説しています。理想の働き方を実現させるためにも、自分に向いてる仕事を見つけたい人は、ぜひ参考にしてください。
「仕事が出来ない=社会人としてダメ」ではない! 原因を探りながら働き方を改善しよう
仕事のミスや進捗の遅れは、誰にでもあることです。しかし、入社後しばらく経っても同じ状況が続くと「自分は仕事が出来ないのかも…」と自信を失ってしまいますよね。
仕事が出来ない状況から抜け出すためには、まず原因を探り、それに合った方法で働き方を見直すことが大切です。あるいは発想を逆転させて、弱みを活かしながらスキルアップにつなげる方法も時には効果的です。
本記事で紹介した方法を実践し、徐々にスキルを伸ばしながら自信を持って働きましょう。

「仕事が出来ない……」と悩み、この記事に辿り着いた皆さんの中には、相当思い詰めている人もいるのではないでしょうか。まだまだこの先伸びしろがあるわけなので、記事の内容を参考に、焦らずじっくりと目の前の仕事に取り組んでみてはいかがでしょう。
赤ちゃんが歩けるようになるのも、ストローを使えるようになるのも、人それぞれのペースがあるように、仕事ができるようになることも、人それぞれのペースがあると思っています。できないことをできないままにしていると成長はないかもしれませんが、この記事をヒントに一つずつ実践をしてみたり、何かしらの工夫、努力をしてみたりすることで、少しずつできることも増えていきますよ。
つまづいたときは一人で悩まずにスクールに行ったり誰かに相談したりしよう
とはいえ、仕事に必要なスキルが足りずに悩んでいる人は、仕事をしながらスキルアップのための学びに取り組むのも手かもしれません。各地域のテクノスクールでおこなわれている在職者訓練を活用し、足りないスキルを磨いてみましょう。教育訓練給付金を活用し、興味のある学びやスキルアップに取り組むのも良いかもしれません。
転職を考えている場合には、次の職場でも同じ悩みでつまづく可能性もあるため、職業訓練や、経産省が推奨しているリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業などを活用し、学び直しをしたうえで転職につなげるのもおすすめです。
いずれにせよ、一人で悩まずに、周囲の人や、キャリアコンサルタントへの相談もしてみてください。厚生労働省が推進している『キャリア形成・リスキリング支援センター』では、ジョブカードを活用し、相談を通じて、キャリアコンサルタントと共にキャリアアップやスキルアップについて、あなたに合った学びを共に検討することができます。対面、オンライン、いずれも相談無料ですので、ぜひ活用してみてくださいね。
就活力診断テストはもう使いましたか?
「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。
面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。
\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/
診断スタート(無料)



















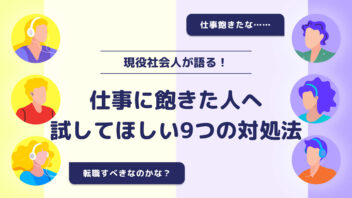
スーパーでのアルバイト経験で申し訳ないですが、仕事が始まって数ヵ月間は「仕事が出来ない」と悩んでいました。というのも、上司との世代が非常に離れている点と、自身の気を遣いすぎる性格が相まって上手く質問が出来なかったからです。
スーパーの一部門に所属する現場仕事ということで、臨機応変な対応や部門内、ないしは部門をまたいだ情報の共有が必要な場合もあります。それにもかかわらず相手の様子を伺いすぎて聞くことが出来ず、業務が滞ることもあったので、自身の仕事力の低さに落ち込みました。具体的な業務というよりは、仕事の基本的なスキルが低いと感じており苦しかったです。